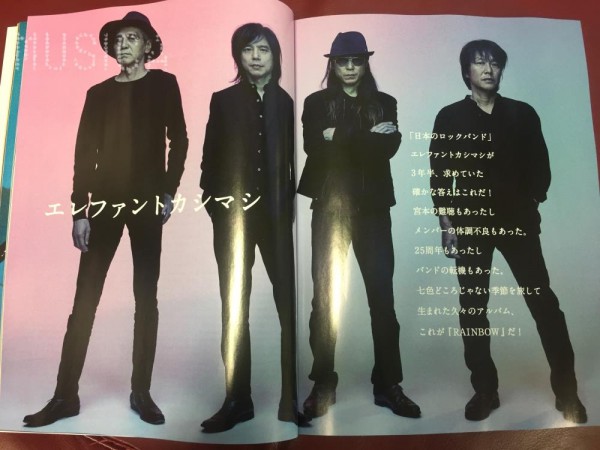きのこ帝国、『猫とアレルギー』で殻を剥ぎ現れた
美しく柔らかな歌の真実

今は自分の宝物を1個ずつ見せてあげてるみたいな感じに近くて。
昔は「あんたらにはわかんないでしょ」って言ってたのが、
「それでも見て欲しいんだよね」っていうのに変わってきてるんです
『MUSICA 12月号 Vol.104』P.94より掲載
■とても素直に佐藤さんの核にあるものを羽ばたかせたアルバムになったと思うんですが、まず何故『猫とアレルギー』というタイトルをつけたんですか? これはリード曲のタイトルでもありますが。
「“猫とアレルギー”という曲は、実は去年の10月ぐらいにできていて。この曲が持ってる空気感をそのままアルバムにしたものを作りたいなっていう構想が芽生えてきてて、そういう流れで作ったので、最終的に元となった曲のタイトルをそのままアルバムタイトルにしよう、みたいな。あとちょっと面白いかな、引っかかりがあるかなというのもありました」
■実際、猫をフィーチャーしたジャケットとアーティスト写真は、以前までのきのこ帝国のイメージとはガラリと変わって。驚いた人も多いんじゃないかなと思うんですけど。
「驚かせたいという気持ちは少しありましたね。やっぱり、この1年は表現において大きな変革があった年だと思ってて。それをわかりやすくヴィジュアルにも反映させるのが一番嘘もないし。悪い意味で驚く人もいるかもしれないですけど、自分達的には作品を聴いてもらえれば絶対納得してもらえる自信があったんで、誤解を恐れずに変化をしたいなって」
■つまり、イメージを一新したいという想いはやっぱりあったんだ。
「そうですね。自分としては今回の変化は、まったく違ったものに変わったわけではなく、今までやってきたことの殻をどんどん剥いでいって、どんどん脱皮を繰り返して、ようやく一番柔らかい部分、柔らかいからこそ硬い殻で守っていた部分を表現できるようになったという感覚なんです」
■まさにそうだと思います。
「そこを出すのは未だに怖い部分はあるんですけど、そこの部分で人と繋がってこそ本当に自分がやりたかった音楽的表現なんじゃないかなっていうのがあって。それをするためだったら、今までこだわってきたあらゆることがどうでもいいもののように思えたんですよね。そういう流れは自分の中ではちゃんと繋がったものとしてあるんですけど、ファンの方の中には、もしかしたら唐突に感じる人もいるかもしれなくて。そこはある種、バンドにとってはリスキーな変化の仕方ではあるんですけど。でも、自分的にはバンドは同じことを続けるよりも挑戦していくべきだと思うし、自分達がより真理に近づいてるっていう自信があるんだったら、それは隠さないであるがままでいるべきだと思うし……っていうのを凄い考えながら作ったアルバムなんです。心的にはフラットに曲を作ったんですけど、このアルバムの持つ意味合いっていうのは自分も深く考えましたし、メンバーも感じるところがありつつ録ってたんじゃないかなと思います」
■どんどん脱皮を繰り返してと言ってくれましたけど、それこそ前作のアルバムの取材から「鎧を外し始めましたよね」っていう話をしてきて。
「はい、してましたね」
■その変化は、きのこ帝国は“東京”という曲以降の『フェイクワールドワンダーランド』、そして『桜が咲く前に』というシングルで提示されてきたと思うんだけど、それにしても今回は完全に鎧を脱いで佐藤さんの核を曝け出した感じがあります。個人的には『猫とアレルギー』は、『フェイクワールドワンダーランド』の次というよりも、その前の『ロンググッドバイ』という作品のネクストヴァージョンというか、あの作品をポップに開いたらこの作品になる、というもののような気がしていて。
「………鳥肌立った(笑)。そうなんです。実は『ロンググッドバイ』と『猫とアレルギー』の世界観は、まったく同じ人に向けて歌ってる作品なんですよ。岩手にいた頃から10年くらい好きだった人がいて、その人のことなんですけど。だからそう感じられるんだと思います」
■ああ、そうなんだ。確かにこのアルバムも、すでに別れてしまったあなたのこと、過ぎ去りし日の愛のことを歌っていますもんね。だから温かな手触りに反して、歌っていることの中には悲しみがあるし。ただ、『ロンググッドバイ』の頃よりも前を見ていて。『ロンググッドバイ』はまだ引き裂かれた、涙を振り払ってさよならを告げていく作品だったけど、今回は何かちゃんと自分の心の中の思い出の棚に収めた感じがあるよね。
「そうですね、引き出しに収めた感ありますね。でも収めたくせにまたそれを引っ張り出してきて、ずっと曲にすると思いますけど(笑)。きっとこの人のことは一生歌っていくと思う。今のところそれが一番自分が震える瞬間だったりするので。もう別れているし、プラトニックのままな分、神格化されてしまってるところもあって(笑)。だから、ほぼストーカーだと思ってくれれば。ストーカーが曲書いてると思ってくれて大丈夫です」
■はははははははははははははは。
「ダメですよね、こんなモラトリアムで。もうちょっと大人にならないと」
■いや、いいと思いますよ。少なくとも表現者としては財産ですよ。
「ふふ。音楽人生の糧にしようと思います。でも、今が幸せだからこそこうやっていい思い出として思い出せるのかなと思っていて」
■ほんとにそうでしょうね。
「きっと今が落ちてる時だったら、言葉にした瞬間に爆発して死ぬ!みたいな、悲しくなり過ぎて戻ってこれなくなると思う(笑)」
(続きは本誌をチェック!)
text by有泉智子
『MUSICA12月号 Vol.104』