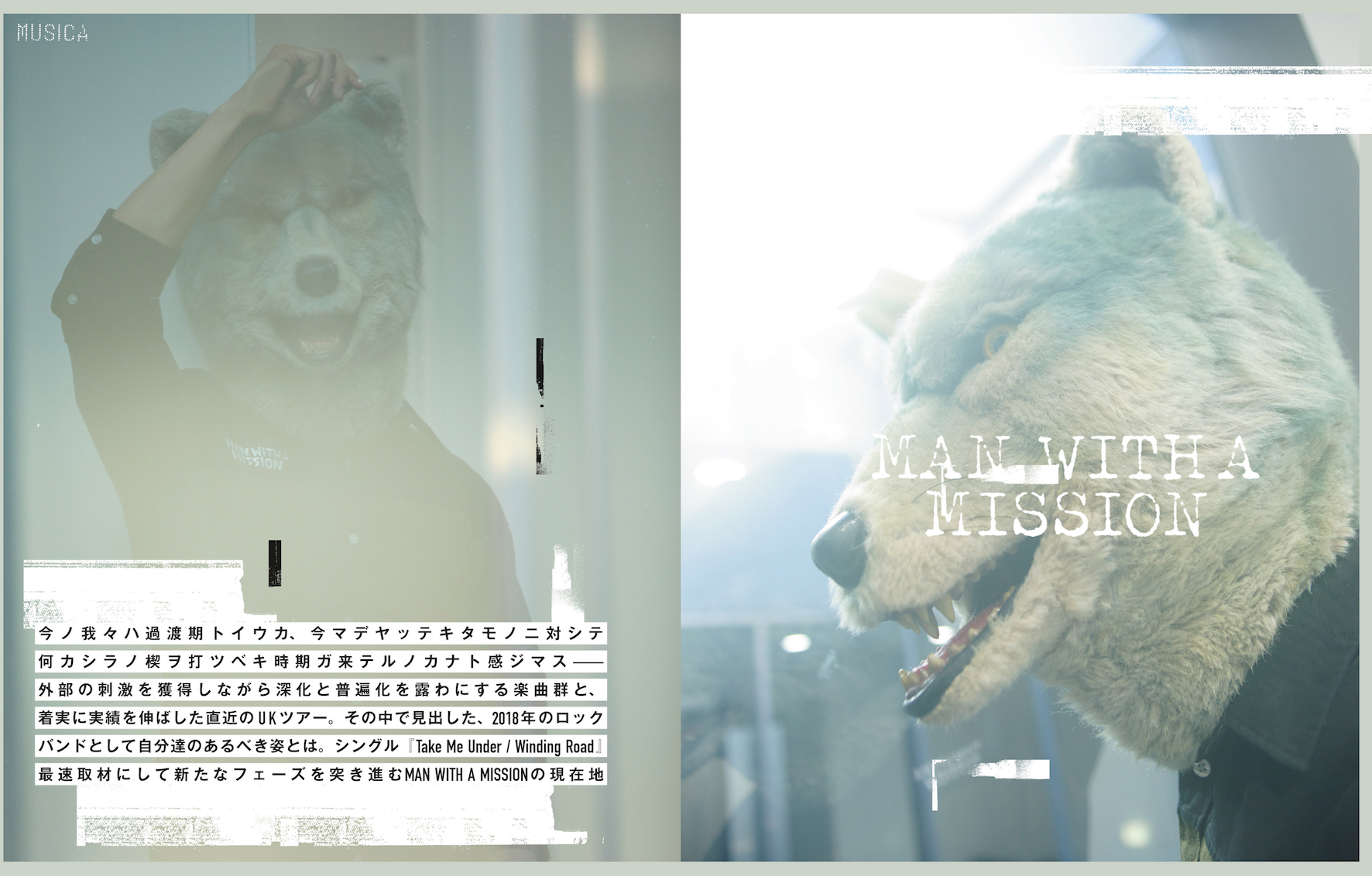ロックバンドに焦がれた原風景と本来の自分を解き放ち、
BLUE ENCOUNTの実像と未来を鮮やかに鳴らした
アルバム『VECTOR』。内なるカオスと闘い続けた日々と、
それを打ち破った光の在り処を、田邊とガッツリ語る

俺は青春を感じたことがない人間だった。だけど、
夢を叶えることのさらに先へ希望を持って進めるのが
青春なんだなってわかったんだよ。だから、バンドをやりたいと思った頃に
思い描いた「音楽」に初めて出会えたんだろうね
『MUSICA 4月号 Vol.132』より引用
■BLUE ENCOUNTがBLUE ENCOUNT本来の形になった、そういう晴れやかな感覚のある作品だと感じました。アッパーなリズムが軸になって、音楽からポジティヴなものがガンガン聴こえてくるアルバムですね。
「嬉しい。これまでとの違いが何かと言えば、『振り切りました』というより、ようやく『吹っ切れました』っていう感覚で。今までを振り返ると、『毎回違うことをやる自由なバンドでいたい』って言ってたくせに、その結果として自分達を自分達で窮屈にしてたところがあったと思うのね」
■それは音楽的な話? それともパブリックイメージの話?
「その全部かもしれない。どっちが先かはわからないんだけど、たとえば『BLUE ENCOUNTのパブリックイメージをどうしていこう』って決めれば決めるほど自分達がわからなくなっていたと思うし。で、そうやって迷いながら、その都度『見つけた』って言いながら前に進む方法でやってきたと思うんだけど、見つけたフリをしていた時もあったのかもしれないなって、今だから思うこともあってね。じゃあ真逆に振り切って音楽だけに集中してみようと思ったら、今度は口をついて出てくるのが『“もっと光を”みたいな曲にしよう』とか、『“LAST HERO”のイメージで』とか、そういうことばっかりになっていって……結局、自分達の固定概念を固めて窮屈にしているのはいつも自分達自身だったなって思うんだよね。まあ、バンドのイメージや立ち位置があるのはいいことだとは思うんだよ? それが自分達の武器になっていくこともあるし。だけど、俺達の場合は以前の曲にただ縛られているだけになっているような気がしてたの」
■だからこそ、作品を出すごとに「誤魔化していた部分があった」とか、「闇が消えない」っていう言葉で自分の中にある壁を表現してきたのかもしれないですよね。その窮屈さや壁をどう打破して、「吹っ切ろう」っていう気持ちに至れたの?
「やっぱり、去年にやった『TOUR 2017 break“THE END”』がデカかったと思う。あのツアーの佳境に差し掛かった辺りから、自分達で自分達を窮屈にしていたところを壊せるようなムーヴメントが生まれていった気がしていて。そこからのテーマが、言葉にしたら少しチープなんだけど『吹っ切ろう』っていうものになっていったんだと思う。そしたら、そもそも『イメージが云々』っていう話自体、BLUE ENCOUNTを組んだ高校時代から『毎回違うことをやって人をドキドキさせたい』って言ってた自分達のやることではないじゃん!って思うようになっていったんだよ。違うことをやるのが目的になるんじゃなくて、とにかく今に素直でいたいっていう話だったじゃんって思い返してさ」
■そもそもの原風景に回帰していった感覚?
「そうなんだと思う。積み重ねてきたものに凄く感謝はあるし、応援してきてくれた人達への感謝もある。で、それが糧になっているんだって考えたら、だからこそ今思い切りできることがあるんじゃないかって思えるようになってきたんだよね――」
(続きは本誌をチェック!)
text by矢島大地
『MUSICA4月号 Vol.132』