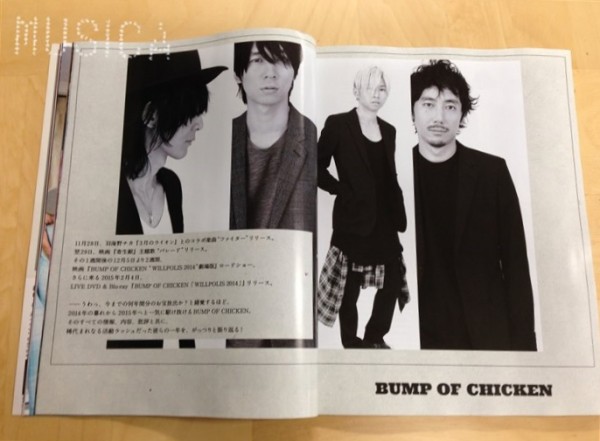plenty、衝動と進化が迸る
新体制第一弾ミニアルバム

新メンバーが入ってplentyは何を提示していくのかっていうことを考えると、
もちろん「曲としてどうか」っていう頭もありつつも、
その上で「芸術は爆発だ!」みたいな、そういう感覚でやりたかった
『MUSICA 12月号 Vol.92』P.110より掲載
■前々号では、一太くん(中村一太/Dr)の加入に至る経緯も含め、もう一度3ピースバンドとなったplentyの意志と手応えを3人で語ってもらったわけですけど、その時にレコーディングしてると話していた作品が遂にリリースされて。
「はい、遂に!」
■収録されている7曲はどれも新体制になってから作った曲だと思うんだけど、これまでの成熟と進化を血肉化した上で、バンドとして新しい体を手に入れたからこその生々しい衝動やダイナミックなエネルギーが迸る作品になっていて。素晴らしいロックバンドアルバムになりましたね。
「俺も凄く納得のいくものができたなと思って。こういうものを作ろうっていうイメージは漠然とあって、それがちゃんとできたんでよかったです。なんか新人バンドのファーストアルバムみたいな武骨さが出したくて」
■武骨というかバンドのダイナミクスが演奏に出ていて、それが凄みになっている曲もあるし。何よりヒリヒリ尖ってるよね。
「そう、それがやりたかった。前みたいに構築していくのも好きだし、もちろんそういう楽曲もこれからもあっていいと思うんだけど、でもやっぱり、今回のこの感じがひとつの武器になるんじゃないかって思ってて。それに、この作り方のほうがやってて楽しいというか(笑)、俺にとっては凄くいいんですよ。バンドやってるっていう感じがする。作業的にもいい意味で俺の仕事が減るから、別のことに時間をかけられるのもいいし」
■その別のことって、具体的には歌詞の作業っていう意味?
「歌詞にかける時間も増やせるし、(3人で)スタジオに入る回数も増えたんですよ! 前の倍以上、スタジオに入ってる。3人でその1曲にかける、その1小節、2小節にかける時間が前とは全然違うから、前よりもバンドの呼吸が合わせられるというか。みんな吸う時に息を吸って、吐く時に吐いて、それさえも共有できて、しかもスタジオで散々やってる分、演奏面に関して何も心配がない状態でレコーディングに行けるっていう……だからレコーディング自体も、ちゃんといい音・出したい音を作って、ちゃんといいテンションのものをレコーディングするっていうところに集中できたし。やっぱり本来こうじゃなきゃ!って感じだった。いいムードでいいテンションでできたから、凄く納得がいく感じになりました。一太にとっては最初のレコーディングだから緊張してるかなと思ったら、全然大丈夫で。むしろ新田(紀彰/B)のほうが緊張してたっていう(笑)」
■実際に一太くんが入って、自分が想像してた以上に制作において化学反応が起こっていったという話は前回もしてもらったけど、その辺は音楽家としての郁弥くんにとってはどういう作用があったと思います?
「一太の加入はやっぱデカくて。あいつはすでに俺の右腕として機能するというか……今、一太はバンドの入場のSE作ってますからね。そういう、あいつ自身に感動することが結構ある。だから、これまではずっと『俺がやってやるんだ!』みたいな感じで音楽やってきたけど、ちょっと信用してみたくなるというか。実際ドラムのフレーズとかも、俺がざっくり投げると一太から凄いのが返ってきたりするから、面白い。今はそうやって、世界観も一緒に作っていけてる感じが面白いんです。前は自分のイメージをみんなにやってもらう感じだったのが、一太のイメージ、俺のイメージ、新田のイメージを重ね合わせてひとつの世界を作る。それはちょっと新鮮。面倒くさいんですけどね、その面倒くささがいいんですよ! しかも完成した時の手応えが今までより全然あるっていうのも凄く嬉しい」
■郁弥くんが完全にひとりでアレンジまで練り上げた精緻なデモを作り始めたのって、たしか“ACTOR”くらいからだったと思うんですけど。
「そうですね」
■その前だったり、それこそ初期の3ピースの頃ともまた違うんだ?
「全然違いますね。前のドラマーがいた頃は俺が作ったものをいかにぶっ壊すかっていうのを考えてたところもあったから。それはそれで面白かったけど、今は3人がちゃんとめざす方向を揃えて、そこに向けて進み出してるみたいな。こういうビルを建てましょうみたいな目的があって進んでる感じ。濃度も違うしね。だからラフなデモを作ってセッションしていっても前とは全然違うし、今のほうが楽しいし」
(続きは本誌をチェック!)
text by 有泉智子
『MUSICA12月号 Vol.92』