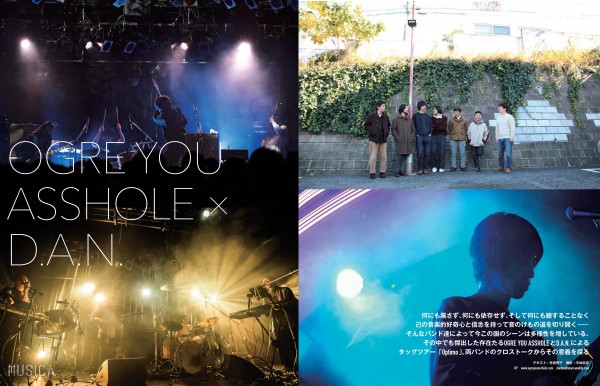アコースティック編成で魅せるthe band apart (naked)と、
荒井岳史(Vo&G)のソロ作が同日リリース! 20周年を前に
自由な活動を展開する現在を荒井単独インタヴューで紐解く

自分達4人で独立したこの数年を一緒にやってきた仲間達っていう感じが
凄くいいし、その仲間を守りたい気持ちが強い。
実はそこに音楽的なものはなくて。新しい音楽を生むためにバンドを
やるのではなく、やり続けるから音楽が出てくるって感じなんです
『MUSICA 1月号 Vol.129』より引用
(冒頭略)
■ここまで、ソロとしてミニアルバムひとつ、フルアルバム3枚出しましたよね。杓子定規的に言えば、ソロワークとしてまずは一周した感もあると思うんですけど。その中で会得できたのは、どういうものだと思います?
「………歌うことが、やっと身近になってきたかもしれないです。特に去年は凄く具合が悪かったから、余計実感したんですよね。具合悪いと、今までやれてきたことも本当にできなくなっちゃうし、もう力任せにはできない。逆に言えば、歌うことっていうのは『こうしないと歌えない』っていうもんじゃないんだなって。それこそ僕の大好きなアーティストにSING LIKE TALKINGがいますけど、まさしくその名前通りにできるのが『歌う』っていうことで。そういった歌のスタートラインに立てた感が出てきたのは、凄く大きいことだったと思います」
■荒井くんがこうしてソロで制作するようになる以前、2009年に吉村(秀樹/bloodthirsty butchers)とダカくん(ヒダカトオル/THE STARBEMS)と一緒に弾き語りの企画をやったじゃない? あれは本当に素晴らしい企画だったし、あそこから、荒井くんにとっての歌の在り方はだんだん変わっていったのかなと思うんですけど。
「ああ、本当にそうだと思います。『only the lonely』っていう企画でしたけど、あれがなかったら、今全然違うと思います。昨日は赤羽で弾き語りのワンマンライヴだったんですけど、そこでもちょうど『ソロをやっている理由はいろいろあるけど、弾き語りを始めた理由は、あの企画を吉村さんと一緒にやったことなんだ』って話したんです。……吉村さんは、僕がソロのアルバムを出す前に亡くなってしまったじゃないですか。だからね、今俺がやっている曲をあの人が聴いたらどう思うだろう?って、本当によく考えるんですよ。『そもそも俺はなんでこれをやってるんだ?』っていう頭になる時も、不思議と吉村さんを思い浮かべることがあって。あの時に、とても大事なきっかけをもらいました。改めて思いますね」
■そして、the band apart(naked)としての2枚目のアルバム『2』。こうしてアコースティック編成で2枚目のアルバムを出すのは、去年出した『1』で得たものが大きかったんだよね?
「そうですね。単純に、曲をアコースティックにリアレンジして演奏する楽しさもあったんですけど、アコースティックで演奏すること自体の味をしめたっていうことだと思うんですね。すると、アコースティックでやる口実が欲しくなってくるというか(笑)。本気でアコースティックもやっていることを早いうちに示したいし、この編成で早いタイミングでリリースすることが、それを示すことになるんじゃないかなっていう想いでしたね」
■自分達がアコースティックにハマった要因は、どういうものなの?
「そこを無理やり客観視すると、普段はエレキギターで相当入り組んだことをやっているバンドなわけで。まあ、アコースティックでもだいぶ入り組んではくるんですけどね(笑)。でも、アコースティックでやると、その入り組んだ形をわかりやすく提示できてる感じがするんです。聴いている人が、わかりやすくthe band apartの入り組み方を咀嚼できるっていうか。その辺が、自分達的にハマった部分だったと思いますね」
■ソロは歌に寄っている音楽で。一方バンアパは、アコースティックになっても歌に寄り添わないんだなっていう(笑)、バンアパの根深い本質がよくわかって面白い作品でした。
「はははははははははははは」
■バンアパの根深い本質がよくわかる作品でした。
「ほんとにそうですよね(笑)。自分でも、the band apartの音像以外の部分までクリアに浮き出てると感じるんです。たとえば『NEW ACOUSTIC CAMP』(というフェス)に出た時に“Eric.W”をアコースティックでやったら、『アコースティックの生のダイレクトな音だからこそ、何やってるかがわかっていいね』って言われたんですよ(笑)。ただのアコースティックっていうだけじゃない、『面白いね』って言ってもらえるのはそこが大きいのかなって。逆に言えば、リアレンジしても結局、入り組んだことをしたがるバンドなんだっていうことも、改めて思ったんですけどね」
■それは、バンアパとしてのスタイルを楽しんだり守ったりしているのか、この4人でやるとどうしてもそうなっちゃうのか、どうなの?
「まさに4人でやるとこうなっちゃうっていう感じだと思います。たとえば木暮(栄一/Dr)が曲を作った時に、『歌を聴かせる曲にしたいからアレンジを控えめにした』っていう旨の話をしてたことがあったんですよ。だけど、意図がそうであっても、現象としては『控えめ』に全然なってない(笑)。木暮の意図を自分達は理解できても、世間的に言うとちっともそうじゃない(笑)、それがthe band apartなんですよね。だけど、結局はそれが俺達の面白みだっていうこともわかってきて。さっきも『歌のスタートラインに立てた』って話しましたけど、歌うことに自覚的になって初めて、『こんなに歌わせてくれないバンドは他にねえな』ってわかったんです(笑)。でも、その大変さがあるからこそ今は楽しくて。単純に歌うことの楽しさはひとりでも実現できるけど、このバンドで歌う楽しさはやっぱりthe band apartにしかないなって。初めて実感できてるんですよ」
■今年リリースした名作『Memories to Go』を聴いていても、今の話そのままだなって思う。このバンドは歌わせてくれないけど、歌わせてくれないことを受け持つっていうより、それでも歌いてえんだっていうせめぎ合いが、明らかに音楽としてのスリリングさに繋がっていると思うんです。
「それはあると思いますね。そういう意味でも、the band apartでやっていることとソロは全然違うと思うし、それはより一層わかってきたことで」
(続きは本誌をチェック!)
text by鹿野 淳
『MUSICA1月号 Vol.129』