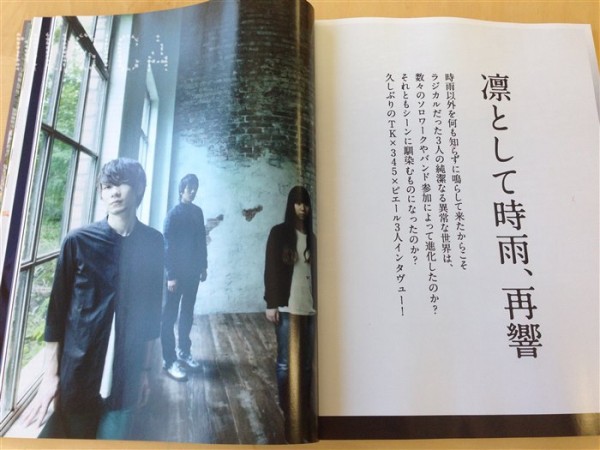きのこ帝国、至高の傑作の誕生で
遂に完全覚醒を果たす!

もっと音楽で人と繋がりたいなって思ったんです。
音で人を圧倒することよりも、
メロディを人が口ずさんでくれることの方が、
自分の中での重要度が上がってきた。
そう素直に思えるようになったんです
『MUSICA 11月号 Vol.91』P.100より掲載
■きのこ帝国のことはこれまでも最大限に評価をしてきたつもりだったし、今度のセカンドアルバム『フェイクワールドワンダーランド』も絶対に素晴らしい作品になることを信じて疑っていませんでしたが、ちょっと今回のアルバムはね、そういう冷静な感じじゃいられないほど、本当に好きで好きでたまらない(笑)。
「先月のMUSICAの原稿も読ませてもらいました。嬉しかったです」
■そこでも書きましたけど、音楽的にはこれまでと何か特別違うことはほとんどやってないにもかかわらず、アルバムとして一枚通して聴いた時に、バンドとしてここでとんでもない飛躍を遂げた作品だと思うんです。どうしてそういう作品が生まれたんだろうってことを、今日はじっくりと訊いていきたいと思います。
「確かに、今まで自分たちがやってきたことから大きく外れることはなく、でも新しいものを作れたのかなって実感がありますね」
■その「新しいもの」というのを、もうちょっと具体的な言葉にするならどういうものなんだろう?
「単純に言うと、メロディアスな曲。いい曲」
■これまでのきのこ帝国のサウンドは、広い意味で言うところのサイケデリックロックの範疇にあったと思うんですよ。で、歴史的にサイケデリックロックのひとつの効用というのは音を聴いて「ぶっ飛ぶ」ことであるわけですけど、今回の作品はサウンドもそうだけど、何よりもメロディのポップさに「ぶっ飛ぶ」んですよね。意識が飛んじゃうくらいポップな瞬間が、何度も何度もやってくる。
「今作のレコーディングに入る前に、『なんで自分は音楽をやってるんだろう? なんで自分は歌を歌ってるんだろう?』ってことを見つめ直したんですね。その時に思ったのは、自分が本当にやりたかったことは、単純にいい曲を書いて、いい歌を歌って、それを聴いた人が感動してくれたり、ふとした時に口ずさんでくれること。理想はそれしかないなって。それを今まで意識的にやっていたかというと、そうではなかった。だから、今回はそれを自分の中で強く意識した上で、メロディを書いて、そこに歌詞をはめていく作業をしていこうと思ったんです」
■これまで、そこを敢えてあまり意識してこなかったのは、どうしてなんだろう?
「これまでも歌を大事にはしてきたと思うんですけど、やっぱりバンドで出すサウンドが好きだったし、どちらかというとライヴを重視してきたバンドだったので、ライヴでいかにサウンドの高揚感を生み出すかっていうことにより意識が向かっていたんですよね。そこに関して、もうやり切ったとまでは言わないですけど、この先もそこを突き詰めていくのではなく、もっと音楽で人と繋がりたいなって思ったんですよ。サウンドで人を圧倒することよりも、自分のメロディを人が口ずさんでくれることのほうが、自分の中での重要度が上がってきたというか。もっとリスナーと近い場所で鳴っているような人間らしい音楽を作って、自分の曲を聴いてくれた人が、まるで自分のことのようにその歌のことを思ってくれたらいいなって、素直に思えるようになったんです」
■それは、レコーディングやライヴを重ねてきたことでバンドとしてひとつ段階を上がることができたから、次の段階として、歌に立ち返るようになったということですか?
「いや、バンドとしての次の段階というより、『自分が本当にやりたかったことに気づいた』と言うほうが正しいです」
■今話してくれたようなことを、バンドのメンバーに言葉で伝えたりはしたんですか?
「そういうのはまったくないです。今までも一度もない」
■そうなんだ(笑)。でも、佐藤さんのその「自分が本当にやりたかったこと」というのは、バンドである必然性はないことじゃないかってちょっと思っちゃうんだけど。あと、きのこ帝国というちょっとアンダーグラウンド臭のする名前さえも、もはや足かせになってくるんじゃないかって。
「バンド名は、変えたほうがいいかなって思ったこともあるんですよ」
■そうですよね。その場の成り行きだけで決まったって話を、前にしてましたよね。
「でも、他にいい名前も思いつかないから(笑)。それに、今のバンドのメンバーとは、10代の終わりから20代の前半という、きっと振り返った時に人生においてとても大事な時期をずっと一緒に歩んできたので。これまでもバンド活動と平行してやってきたように、ソロのことも考えてないわけではないんですけど、曲のよさとバンドサウンドが化学反応を起こして生まれるものというのが、自分にとってのゴールなんじゃないかなという気はしてます。音楽、特にポップミュージックには、バンドではできないこともありますけど、一方でバンドにしかできないこともあると思うから。きのこ帝国は、そのバンドでしかできないことをやる場所だと思っているので。そこの部分での葛藤だったり摩擦だったりというのは、自分の音楽への意識が変化していく中でも、そんなに大きいものではなかったですね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 宇野維正
『MUSICA11月号 Vol.91』