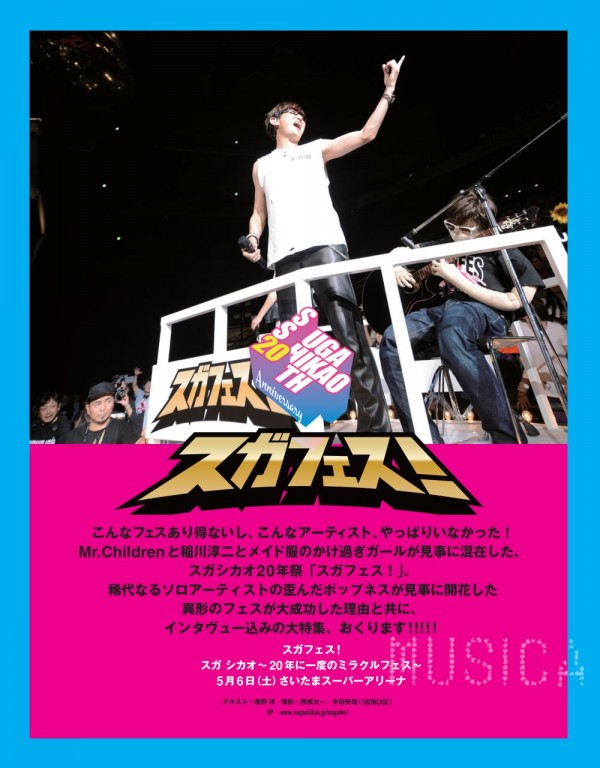傑出した音楽を作り続けてきたplentyが
あまりに突然の解散を発表。
バンドの中心人物・江沼郁弥がその理由と胸中を語り尽くす

俺、「次は“拝啓。皆さま”みたいなのを作ろうかな」
ってポロッと言ったの。それは打算だったんだよ。
一瞬plentyらしさみたいなものにあやかろうとしちゃったんだろうね。
恥じたね。きっぱり辞めようと思った
『MUSICA 6月号 Vol.122』P.110より掲載
(前半略)
■そもそも解散に至る契機はいつ、どんなことから始まったんですか。
「『life』のレコーディングが終わった後ですね。一太(中村一太/Dr)がplentyを辞めるって言って………そこから始まりました。一太から何回か辞めたいって言われて、でも最初はよくわからなくて、『まあ、そういう時ってあるよ』みたいな感じだったんだけど」
■自分もよく「もうplenty辞めてやる! 解散だ!」って言ってたし。
「そうそう。『俺だって毎分毎秒思ってたよ!』みたいなことを言って返してみたいな、そういうのが何回かあって。最初は一太も詳細をあまり語らなかったんですよ。だから俺も全然腑に落ちなかったの。でも俺がしつこく訊いたら、『ひとりでやってみたくなった』って言われて。で、たぶんそれが本音だなと思って。でも、そもそも一太に関しては、plentyの活動以外にもいろんなバンドでもやったり、課外活動みたいなことしてもいいよっていうOKは出してたから、それなのに辞めたいっていう意味が俺はよくわかんなくて……ってなったんだけど、よくよく考えたら『俺、その気持ちわかる』って思っちゃったんだよね。たぶん挑戦なんだよね、一太にとっては。一太はこれまで音楽活動において0から1を作るっていうことをしてないっていうか、そういう役割じゃなかったから」
■plentyでも、そしてthe cabs時代も自分で曲を作っていたわけではないし。
「そうそう。でも、一太は自分で曲を作りたくなったというか、自分自身で0から音楽を作りたくなったんだろうなって思って。で、自分自身で音楽を生み出したいっていう気持ちが生まれた時に、それはplentyに在籍しながらやるっていうことじゃないんだって思う気持ちが、俺にはわかっちゃったんだよね。……一太が入ってからplentyっていう体質が変わって、俺がひとりで組み上げていくっていうよりも、またそれをメンバーと一緒に作り上げていくっていう形になったでしょ?」
■そうですね、そして郁弥くんはそこに大きな喜びを覚えていたよね。特に一太くんとは、アレンジのやり取りもかなりしてたし。それこそ、郁弥くんが作ったデモをさらに一太くんがアレンジしたデモを聴かせてもらったことがあるくらいに。
「うん。ふたりでプリプロ入ったりもしたしさ。そういうことをやっていく中で、自分ひとりでもそういうことをやってみたくなったっていう気持ちもわかるし。そうだよなって。そもそも人と何かを作るっていうのはそういうことが起こる」
■相手のクリエイティヴィティを刺激するっていうことでもあるからね。
「そう。たぶん彼は、plentyでいろんなことをやってみて、そこを刺激されたんだよね。だから結構納得してるけどね」
■ただ、一太くんが抜けることになっても、選択肢として、このままplentyを続けていくっていうことはもちろんあったと思うんですよ。
「選択肢としてはね。我々にはなかったけどね(笑)」
■でも実際、サポートを入れて続けるっていう選択肢はあったわけじゃない?
「そうね、あった。けどさ、選択肢はあったけどさ、なしだよね?」
■と、郁弥くんは言うけど。それが何故なしなのか、私にはわからなくて。
「確かに論理的にはそういうやり方もあるよ。また新田(新田紀彰/B)とふたりで、サポートのドラマーを入れてやるっていう。でも、それをやるのは楽しくないと思っちゃったんだよね。それって補完作業っぽいじゃん。plentyというものを守るための手段っていうかさ。もちろん、俺自身がそのやり方が本当にいいなって思えたらいいんだよ。現に前にひとり辞めた時は、そうやって続けたわけだし。でも今回はね、それがあんまり魅力的じゃなかったんだよな」
■それは、あの時と今とでは、何が違ったからなの?
「そもそも、そういう気持ちで一太を入れてないんだよ」
■というのは?
「またひとり欠けてもいいと思って、一太を入れたわけじゃない。だって3年サポートを入れた体制でやってさ、そこからまた新しいドラマーを入れるっていうのも、それはそれでリスクじゃん。でも、それでも一太を入れたわけで」
■当時のことを振り返ると、一太くんを入れる前はレコーディングドラマーとしてサカナクションのエジー(江島啓一)、そしてライヴにおいてはドラマーに中畑大樹さん、ギターにヒラマミキオさんという強力なサポート陣を迎えた体制でやっていて、その完成度も表現力ももの凄く高くて。だから語弊を恐れずに言えば、純粋に音楽的な部分で考えると、あの体制を崩す必要はなかったと思うんだけど。でも、それでも郁弥くんはバンドでありたいと願って、本当の意味でバンドとして音楽を作って奏でることを求めて、一太くんを正式メンバーとして入れたわけだよね。
「そう。だから、『また抜けてもいいや』みたいな気持ちは全然なかったし、本当に覚悟を持って一太を入れたんだよね。で、実際に一太を入れてplentyは凄く変化して。変な意味じゃなくて、誰にも頼ってない感じがしたというか、メンバーだけでちゃんとバンドをやれてる、音楽をやれてるっていう感覚になることができて。3人のイエス/ノーが大事なんだっていう感覚でやれてたから。もちろん、いろんな人のサポートはあるんだけど、でも少なくとも俺はそういう気持ちでやれてた。そういう状態――要はちゃんとこの3人がplentyなんだっていう状態になったからには、それは誰かひとりでも欠けたら終わってしまうものだったんだよね。……新田との年月のほうが長いから、みんなそのことを言うんだけど、でも年月じゃないんだよね。もちろん新田とふたりでやるのが嫌だっていう話でもまったくないし。そういう話じゃないんだよね。期間がどうとか思いがどうとかじゃない」
■つまり、それくらい一太くんが入ってからのplentyは、この3人以外では替えのきかないレベルまで、ちゃんと本物のバンドになれていたってことだよね。
「うん。少なくとも俺にとってはそうだった。替えがきくものではなかったかな。でも、もちろん一太が抜けることだけが解散の理由じゃないんだよ。というか、一太のせいではないんだよ。誰も一太のせいにはしてないし」
■そうだよね。替えがきかないってことはあるにせよ、「一太くんが辞めます、だからplentyを解散します」っていうふうに直結的に結論が出せるようなことじゃなかったと思うんですよ。実際、『life』を作って、“born tonight”みたいな最近の自分の音楽的興味をplentyに落とし込んだ楽曲もできて、これまでのplentyの音楽性とは違う新たな広がりと手応えを感じてたと思うし。『life』に収録された以外にも、もっとそういう方向に振り切った曲も作ってるってインタヴューでも話していた通り、あの先に広がるplentyの音楽的な可能性だったり、自分自身の音楽家としての可能性っていうものを視野に捉えてたと思うんだけど。そういうものが断たれてしまうことに対する悔しさみたいなものはなかったの?
「でも、それもあの3人でのplentyの次の可能性だったから、その3人であるっていう前提がなければ成り立たないものだし。……でも確かに、一瞬、『またふたりでやりましょうか』とはなったの。一太が本当に抜けることになった後に(事務所の)社長に呼ばれて、これからどうするかっていう話し合いをして。その時に一瞬、ふたりでサポート入れてやってみましょうかって話にはなったんだけど。でも、それで何を作ろうかなって考えた時に、俺、『次はまた“拝啓。皆さま”みたいなのを作ろうかな』ってポロッと言ったの。その時に『ああ、終わったんだな』って思った」
(続きは本誌をチェック!)
text by有泉智子
『MUSICA6月号 Vol.122』