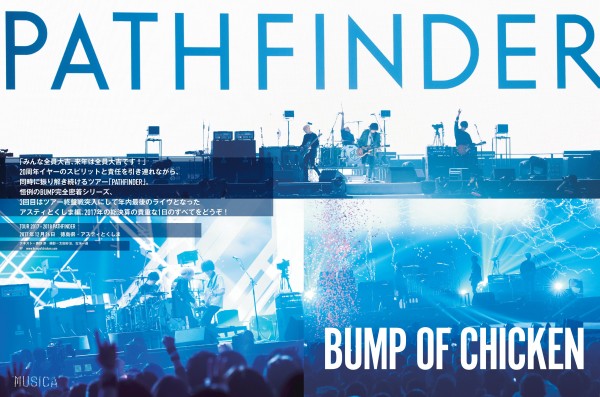Dizzy Sunfist、メロディックパンクの未来を照らす
完全覚醒の決定打、『DREAMS NEVER END』完成!
あやぺたの音楽観に、正面から踏み込む初ソロ取材

女ヴォーカルのメロディックパンクっていうことで軽く聴くヤツに対して、
「なめんな!」っていうのは強かった気がします。「夢は死なへん」って
言ったことをある程度叶えてこられた1年間やったし、
がむしゃらにやってみようと思えたんです
『MUSICA 2月号 Vol.130』より引用
(冒頭略)
■全体で言うと、明るかったり楽しかったりするだけじゃない、聴く人の胸倉を掴んででもメッセージを伝えようとするストロングスタイルのパンクアルバムになったと感じて。ご自身ではどういう感触があります?
「自分としても、とにかく歌いたいことと伝えたいことを真っ直ぐやろうと思ったアルバムですね。で、それができたアルバムやと思ってますね。歌詞もメロディも真っ直ぐなものとして私の中にあり過ぎて、メンバーにも『これがやりたいねん!』って結構押し通す感じだったので」
■今このタイミングで、真っ直ぐやろうっていう気持ちをより一層押し通したかったのは何故なんだと思いますか。
「やっぱり他のバンドみたいに複雑なこともできないし、いろんなバンドと一緒にやってきたことで、自分にできるのは真っ直ぐにやり続けることしかないなって思ったんですよ。同世代のバンド達も売れていく中で改めて自分の武器を見つめ直したら、やっぱり真っ直ぐにやることしかないなって。真っ直ぐやることに真っ直ぐになったというか」
■今おっしゃった「真っ直ぐ」っていうのは、この作品を聴く限りでは、ハイスタの世代、HAWAIIAN6やdustboxの世代……と脈々と続いてきたメロディックパンクの正攻法を真っ向から受け継いで、とにかくあやぺたさんのいいメロディを歌い切るっていう意味でのストレートだと感じたんです。そういう意味では、いろんなバンドが売れていく中で新しさやオルタナティヴな在り方を目指していく状況を見た上で、こういう正攻法のカッコよさが見過ごされてないか?っていう気持ちもあったんですか。
「それはあったと思います。もちろん、他のバンドがダメとかそういうことではなく、そういう状況を見れば見るほど、自分の武器は真っ直ぐさしかないんやなっていうことがハッキリしていったんですよ」
■あやぺたさんにとっての真っ直ぐさとはどういうものなんですか。
「難しいなぁ(笑)。でもやっぱり、何に対しても素直になれるっていうことやと思います。やりたいことやりたいし、やりたくないことはやりたくないし……そうやってハッキリと言えることやと思います」
■それはまさに歌い続けてることですよね。夢を持つっていうテーマは、真っ直ぐでいいんだよって歌うこととも直結するわけですけど。それは、昔からあやぺたさんが強く思い続けてることなんですか。
「いや、全然そんなことなかったですね。むしろ最近、そうやって真っ直ぐに生きていきたいっていう気持ちが強くなったんやと思います。たぶん昔は、そういうことを考えることもなく真っ直ぐに生きていたと思うんですけど。でも今は、それをちゃんと突き詰めてみようって思って。ただ、意識して何かを変えてみたっていうわけでもないんですよ。自分から出てくる曲がそうなっただけで。きっと、経験値なんですかね。いろんな人と出会うことで人間的にグレードアップできたんかなって」
■具体的に言うと、どういう出会いが影響をくれたと思います?
「映像の中でしか見てこなかった人達と対バンしたり、話したりすることが増えたんですよ。言ってみれば、到底触れ合う機会なんてないやろうなって思ってた人達とも一緒にライヴができたりして……この数年で、そういうことがどんどん現実になっていったんですよね。ハイスタももちろん、HAWAIIAN6やdustboxとも一緒にライヴできて、ライヴの後も一緒にお酒飲めたり……高校生の頃の自分からしたら、あり得ないことが増えてきて。その結果として、あいつら何でも真っ直ぐにやってるな! やりたいことやってて楽しそうやな!って思われてたら最高やと思います」
■そうして自分の中の「こうしたい」を無濾過で放出できるのが、あやぺたさんがメロディックパンクに惹かれた理由でもあるんですか。
「そうかも。歌もギターもドラムもベースも、すべて全力で鳴らすじゃないですか。みんなが全力で一気に行く瞬間。あれに胸焦がれるんです。難しいことやってなくても、全力が重なった瞬間の全力に憧れてしまう」
■これは全然違う話かもしれないですけど、素晴らしいメロディックパンクを鳴らす人って、その音楽のシンプルな構成からは考えられないくらい面倒で複雑な脳内の人が多いと思うんです。本当はもの凄く暗かったりする人が、それこそ全力の輝きへの憧れを託してるというか(笑)。
「ははははははは! でも、それはなんとなくわかります(笑)。まさに憧れですよね。そう考えたら……普段の自分はもの凄い不安症なんですよ」
(続きは本誌をチェック!)
text by矢島大地
『MUSICA2月号 Vol.130』