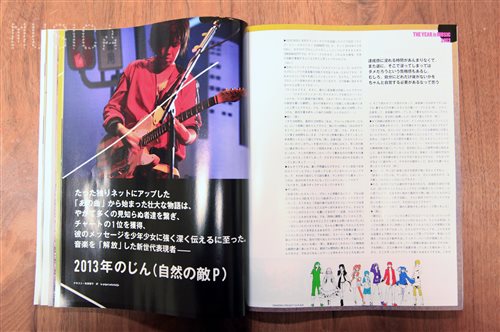9000人の超満員と共に歌を響かせた
高橋優の初武道館ライヴ完全密着!

名実共に、武道館、ロック、伝説を高橋が超えた、
「奇跡を凌駕したリアル」が爆発したライヴ!
素晴らし過ぎる一夜に
完全密着レポート&インタヴュー
『MUSICA 1月号 Vol.81』P.96より掲載
とても晴れ渡る、そして武道館近くの皇居をたくさんのランナーが日差しを受けて走り続ける午前11時30分。まだサポートミュージシャンも入っていない中で、高橋優は武道館入りした。当初は12時半入りの予定だったが、2日前に急遽「1時間早く入りたい」という話が彼自身からあったようで、そうなったようだ。
スタッフが慌ただしく動き回る暗闇の中で、ステージや客席をぐるっと見渡しながらいろいろ考えている高橋が、「入ってくる時にも見たんですが、こんな早くに来ているお客さんがいるんですよ。僕はね、いろいろやることがあるじゃないですか、今から。でも、みなさんどうするんですかね?」と言うので、「みんなにとっても今日は特別な日なんだよ。ここにいることで、すでにいろいろなことが始まってるんだと思うよ」と告げると、「あー………確かに僕はね、寝れなかったんですよ、昨日の夜から。それはね、もうしょうがないですよね。でも、ファンの人も寝れないって言って来てくれる人が凄く多かったんですよ。これって、そういうことなんですかね? 恵まれてるってことですよね」と話す。
武道館のアリーナほぼ真ん中でさらに立ち話をする。
「時代に取り込まれちゃいけないなぁって、最近さらに思ってて。そんなことはわかってるつもりだったのに、ついつい自分が取り込まれちゃってる気が最近してて。『沈黙を破れ』ってスローガン掲げてアルバム作って、それでも取り込まれるんですよ。……なんなんですかね……だから、最近曲が作れなくなっちゃって」
■それ、去年の同じ頃も言ってたよね。
「いや、違うんですよ。前はね、どういうモードで音楽をやるか悩んでいて、もうこういう曲は作りたくない、歌いたくないって感じだったんですけど、今は違うんですよ。曲を作っても作っても、どういう曲を自分がやりたいのかわからなくて、全部ボツにしちゃうんですよね。ちゃんと作って、ハードディスクとかに入れても、全部削除しちゃって。……スタッフからはもったいないと、せめて記録しておけばと言われるんですけど、今はスタッフにすら嘘をつきたくない。だから結果的に曲が表に出てこないんですよ」
■でも大切な時期だよね、この武道館ライヴをやった後というのは。
「わかってるんですよ、それを自分でも。だからなのかもしれないですけどね。……だって、いろいろな先輩方が武道館でライヴをやって」
■あまり男性ソロアーティストがやる場所でもないけどね。
「確かに。でもナオト・インティライミさんとか秦基博さんとかいろいろな方がやるじゃないですか。そうそう、星野(源)さんもですよね、元気になったんですよね? よかった! でも武道館をやった後って、それで一段落なのか、ゴール地点なのか、みなさん、いろいろあるじゃないですか。僕はそういうのを見てきたから、このライヴの後ですぐに動きたいんですよ。すぐにいろいろなアクションを起こしたい。でもそのための曲が作れないんですよね……」
■武道館がどうのではなく、必然的にここでライヴをやると、それがシーンや人からは節目として見られるから、そこで何かを持ち帰れるライヴができるといいね。
「そうですねぇ、もうあと6時間後ですか。……そういえば、ポール・マッカートニー行ったんですよ。凄くいい機会でした。もう、溢れんばかりにビートルズの曲をやって、アンコールでは福島へメッセージを寄せて“Yesterday”を歌うんですよ。凄いですよね、『もう過去には戻れない、取り戻せない』って日本人を前に歌うんだから、ビートルズやってた人ってやっぱり凄いですよね。そういうライヴを4日前に見て、そしてそのビートルズが初めて立った武道館に――」
■日本武道館が武道以外に会場を貸した初めての機会だったわけだからね、1966年のビートルズの武道館公演は。
「そうだったんですか! そのビートルズのポール・マッカートニーを見た直後に武道館でライヴをやるのはなんらかの意味があると思って。それを含めて楽しみなんですよ」
そう言いながら、高橋は楽屋へ吸い込まれて行った。
(続きは本誌をチェック!)
text by 鹿野 淳
『MUSICA1月号 Vol.81』