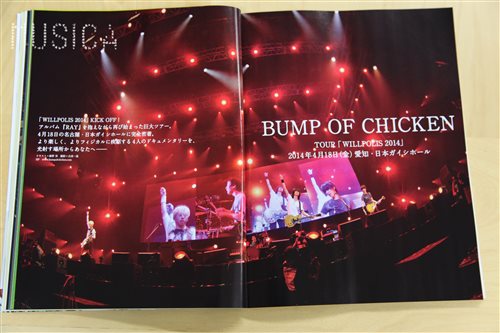Base Ball Bear、かつてない難産からかつてない最高傑作
――約3年ぶりのフルアルバム『29歳』堂々完成

僕、本心から曲を作るのができないタイプだったんです。
自分の心が部屋だとして、「本心」が入ってるドアがあるんですよ。
でもそのドアにはドアノブがなくて、溶接されているんです……。
で、ドアの向こうにあるらしい「本心」に必死に耳を当て、
「本心ってどんななんだろう?」ってふうに思ってる、
それが自分だったんです。だけど――
『MUSICA 6月号 Vol.86』P.98-105より掲載
■遂に難産なアルバムが生まれ落ちました。かなり長かったと思うんですよね、ここに至るまで。
「ほんとそうですよね。一度諦めたり、いろいろあったアルバムですから、でき上がった時は不思議な気持ちになったり(笑)」
■前作『新呼吸』が集大成感や達成感があったことを含め、その後に燃え尽き症候群もあったことも含め、これだけ時間がかかったのかなと思うんですが。この3年間を振り返って、どうですか?
「3年間………結構考えっ放しだったかもしれないですね、このアルバム。テーマ探しみたいなのがずっと断続的に続いてるっていう感じだったから。『新呼吸』がよっぽどだったんですよ、自分の中で。単純にアルバムの内容だけじゃなくて、アルバムを発売するまでの仕掛けをプロモーションっぽいところで引っ張るんではなく、作品のコンセプトとしてのシングルをちゃんと打って、最後アルバムに辿り着くっていう、正直言ってかなりわがままを通してやったアルバムだったし――」
■自己世界としてのある意味完璧なストーリーを作ったアルバムだったんだよね。
「だからあのアルバムを超える自分の中でのテーマがないといけないなってずっと思ってて。それはつまり、『何を歌うか?』っていうことなんですよね。それを考えるのに3年かかっちゃったっていうのが正直あります。『新呼吸』で辿り着いた考え方というか自分の意見っていうのをまた自分の中で噛み砕いて、反芻して、今自分がどう思ってるかっていうのを何度も何度も考え直すんだけど……でも、やっぱり『新呼吸』で1回上り切っちゃったから、なかなか下れないというか(笑)。そういうので苦労してましたね」
■『新呼吸』はあの時伝えた通り、本当に素晴らしい作品で。で、今回のアルバムも相変わらず素晴らしい作品だなと思います。でもいろんな意味で装いが違うアルバムになったよね。まず、「サウンド」と「歌詞も含めた歌」のふたつに分けて、サウンドのほうから話をしていきたいんですけど。
「はい」
■僕はサウンドが一番予想外だったんですよ。非常にバンドサウンドな作品になったことが意外だった。ここに至るまでの間の小出くんの過程でいくと、いろんな人とのコラボレートがあったり、今の日本の音楽シーンなりのサブカルチャー――ヒャダインやアイドルとか、そういうところとのリンクも表現世界の中にあったし。いろんな意味でもうちょっと脱・バンド的な作品になるのかなと思ったんですけど、『新呼吸』よりもさらにバンドサウンド然としてる作品だなと思ってて。そこは本当に意外だった。
「確かにそうなんですよ。ここまでの流れでいくと、より脱・バンド的な方向に行きたがるのかな?と僕も自分で思ってたんです。で、いざ今のバンドのモードだったり、自分も含めたコンディションみたいなものを1回見直してみたら、むしろ凄くバンドらしくなってきたなって思って。たとえば、今までのコラボレーションだったりとかフューチャリングをしていく中で、よりバンドっぽさっていうのが備わってきていて。それは最初にアルバムのプリプロに入った時にそう思ったんですよね。今この場で鳴っている、4人で『せーの』で出しましたっていう音の感触がいいから、ここをちゃんと届けられたほうがより今のバンドのモードになるなって思ったし。それってずっとやりたかったけど、意外とできなかったことだったんですよ。っていうのも、Base Ball Bearはギターロックの耐久性を検証するっていうのを批評的な意味も込めてやってきたバンドじゃないですか」
■まさにそうだね。
「だから意外と僕ら4人が『せーの』でポンッと出したものいいから、それをまんま作品にしたいっていうのが意外とないバンドだったんですよ」
■THEE MICHELLE GUN ELEPHANTは遥か彼方にってことね(笑)。
「ははは、そうそう。そこに対してのリスペクトだったり憧れは常にあるんだけど、でも僕達はひねくれ者だからそれは敢えてやらないっていうのでずっといたんです。でも、ここへ来てやっとそれをやれるだけのそれぞれのメンバーのポテンシャルが備わってきたなと思ったんですよね。で、やってみたと」
■それは人間的な問題なのか、もしくはいろんなコラボレートによってバンドのスキルが高まって、結果的にボトムアップしていったって感じなのかな?
「たぶん両方だと思いますね。演奏してる時にメンバー同士で『なんか……大人になったね』みたいにしみじみ言い合うシーンが何度かあったりして(笑)。それは単純に自分達が鳴らしてる音っていうのもそうだけど、音から感じる人間的な部分っていうの込みで、『大人になったね』って言い合う気持ち悪いシーンが結構ありました」
■言ってみればさ、デビューの時期からずっと思春期からの逃避みたいな気持ちがこのバンドにはあったわけじゃない。その逃避から今こうやって、4人のバンドやお互いに対する気持ちが「実態」になったのは感慨深いよね。
「そうですね。学生時代からずっと一緒にやってきてるバンドだからこそ、確かめ合える部分なのかなとは思いましたね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 鹿野 淳
『MUSICA6月号 Vol.86』