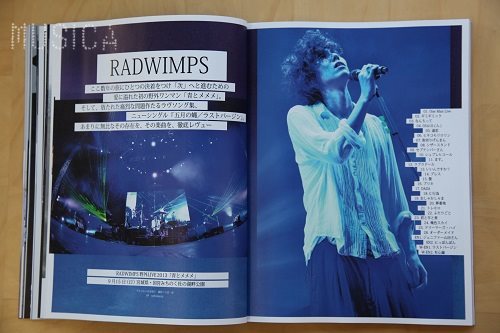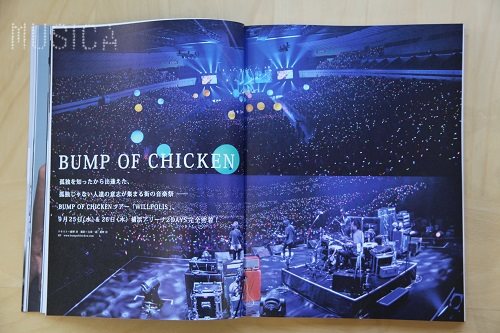米津玄師、新たなステージ。
研ぎ澄まされた彼の表現に深く迫る

妄信的になれたら
どれだけ楽だろうと思うんですけど。
……俺の世代って凄い自意識過剰なんですよ。
でも、他人からどう見られてるか意識しない人間
っていうのは否応なく美しいもので。
『MUSICA 11月号 Vol.79』P.90より掲載
■前作の“サンタマリア”という曲は、それまでの米津くんの音楽像から大きく踏み出した変化作にして名曲だったんですが、今回はどの曲も、いい意味で非常に米津印なサウンドと歌の感じと、そして米津印な歌詞を研ぎ澄ませた形の楽曲になっていて。自分が持っている武器を如何なく発揮した印象があるんですけど、どういう意志の下にこの作品を生み出したんですか?
「“サンタマリア”が今までと全然違うことをやったんで、次に何やるかっていったら今までと同じことやろうかなっていう(笑)。単純に、激しい曲をやりたくなったっていうのがありますね。歌詞に関しては、詩的表現っていうのをなるべく排除する形で。いろんな意味に取れる振れ幅の大きい歌詞っていう感じではなくて、ストレートに直球な歌詞を書こうと思って作りましたね」
■そう思ったのはどうしてだったんですか?
「曖昧にしていたくないなって思ったからです。これまでやりたいことだけやって、やりたくないことに関しては曖昧に曖昧に、後回しに後回しにしてきた人間なんで。でも、もう曖昧になってはいけないなと、それは楽曲に対しても思いました」
■それは、何かひとつ区切りがついたってことなんでしょうか。たとえば前回のインタヴューで、あの時期に“サンタマリア”を作ることは、自分にとって禊みたいな意味合いが強かったっていう話をしていただいたんですけど。その禊ぎが済んだっていうことが関係してるんですか?
「前に話した通り、“サンタマリア”は自分の中でどうしようもなくなってた時に作ったんですね。あれを作ってシングルにするしかなかった状況だったんですよ。だから今になって自分がやってきたことを振り返っていくと、必然的に“サンタマリア”の前か後かで話すことが増えてるんですよね。だから、確実に“サンタマリア”を作って出したっていうのは自分の中で凄く大きなことで、だからこそ直接的な表現を取らざるを得ないと思いながらやってます。それを吹っ切れたと言っていいのかどうかわからないですけど」
(続きは本誌をチェック!)
text by 有泉 智子
『MUSICA11月号 Vol.79』