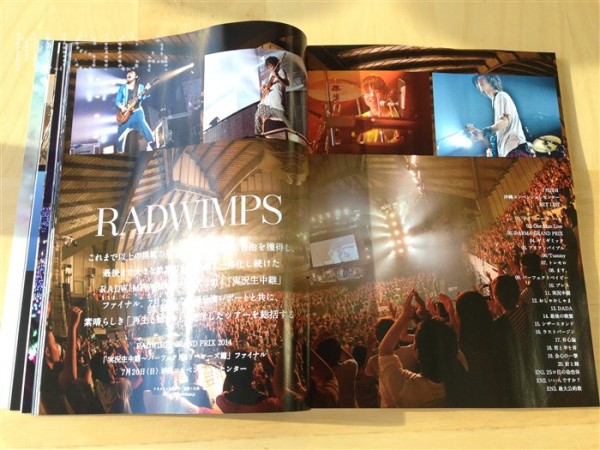TK from 凛として時雨、ロックを越えた狂気と普遍性、
ロックだからこそ生まれるポップ――
確かな「自分」を響かせた金字塔
『Fantastic Magic』に感嘆する

「結局、変われないんだな」っていう絶望もありますし、
でも、「ちゃんと自分の中には俺がひとりいるんだな」
っていう確かな想いもあって。だったら、
それを受け入れて音を生み出していくほうがいい
っていう選択をしたんです
『MUSICA 9月号 Vol.89』P.92より掲載
■期日ギリギリにできたんだよね?
「そうですね。いろいろありまして(笑)」
■そんなに困難を極めたんですか?
「いや、ギリギリで1曲追加したんですよ、自ら。ネガティヴな『できない、できない』っていう感じよりは、9曲のアルバムでいくのかどうかっていうところで、最終的なトータルバランスを考えて。こういう曲が1曲欲しいというよりは、1曲完全な新曲が欲しくて、やれるところまでやっていたらギリギリになりました」
■ちなみにその曲ってどれなんですか?
「“Spiral Parade”(8曲目)ですね」
■あ、やっぱり。
「はははははは。やっぱりわかります?」
■非常にこの曲は異端性があるので(笑)。その話はあとで聞きたいんですけど。まず、この10曲を聴いて最初に思ったのが、TKのキャリアの中でこれが一番の名作だということで。
「ほんとですか? 鹿野さんにそれを言ってもらえると嬉しいです」
■バンド活動を通じて、すべての中で一番素晴らしい作品だと思いました。もちろん、凛として時雨があるからこそ生まれたソロとしての傑作なんですが。ご自分の実感としてはどうなんですか?
「『flowering』を経て――あれは、ソロの形でのアルバムとして一発目だったんで、ある種、僕が何者なのかわからない状態から作れる作品だったと思うんですよ。あれはまるでセカンドヴァージンみたいな感覚だったから(笑)、カラフルなアルバムになったと思うんですけど。ただ、カラフルだけど、一体自分は何者で、どういう色なのかっていうのは、あんまり自覚できなかったんですよね。でも、それを経たことで、今回はいろんなものを削いで、そこにまた色をつけていく感じだったので、自分が今何色なのかっていう明確なものを感じられるアルバムになった気がして。前作よりもさらにソロとして成立したなっていう感覚はありましたね」
■このアルバムを「TKのキャリアの中で一番いい作品なんじゃないか」と思った理由はふたつあって。ひとつはソングライティングが素晴らしいんですよ。それはこのソロに限らず、時雨からずっとやってきた中での進化と成熟によるものだと思って。ふたつ目は、その素晴らしいソングライティングがある程度裸だから、その曲の素晴らしさの理由やパーツがダイレクトに聴こえてくる素直な作品になっているんだよね。『contrast』の時も、「もっと人に聴いてもらえる音楽をやってるはずなんだけど、ちゃんと届けられてないんじゃないか」という想いがこのソロプロジェクトのひとつのモチヴェーションなんだという話をしてくれたけど、そういう部分も踏まえて、このアルバムが素晴らしいのだと思います。
「『伝わってないな』っていう実感がフラストレーションにもなりますし、その反動が『伝えたい』っていう気持ちに本当に直結したという感じはありましたね。やっぱり凛として時雨をやってきて、そこからソロっていう形になったことで『まだまだ全然伝わってないんだな』って実感もしましたし――それも、弾き語りも始めたワケだったんですよ。で、弾き語りでソロの曲も時雨の曲を演奏すると、結構な数の人に『こういう綺麗なメロディだったんだ』とか、『こんな綺麗な言葉だったんだ』と言われて(笑)。さらに、『正直、凛として時雨は、刃物に次ぐ刃物みたいなイメージだった』と(笑)」
■はははははははは。
「もちろん、尖った部分が人の目や耳に突き刺さったことによって、凛として時雨が確立できたのもあるんですよ。だけどそれと同時に、尖ってない部分もあるってことが凄く見えづらかったんだろうなって……だとしたら、自分はまだまだ何も伝えられてないんだろうし、本当に伝えなきゃいけないって想いが自然と大きくなって。それが今年の『contrast』からの流れでしたね。で、その集大成みたいな作品が今回だと思うんです。もちろんまだまだ途中段階ですけど、『ソロだから好きなことやってやれ、聴いてもらえなくてもバンドがあるからいいや』みたいな気持ちはまったくなくて。逆に、ソロはソロでバンドのライバルでありたいし、バンドは聴けないけどソロは聴けるっていう人がいてもいいと思うし、その逆もあっていいと思いますし。いろんな間口が広がることによって、自分の音楽に触れてくれる人が増えるといいなっていうのは凄くありましたね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 鹿野 淳
『MUSICA9月号 Vol.89』