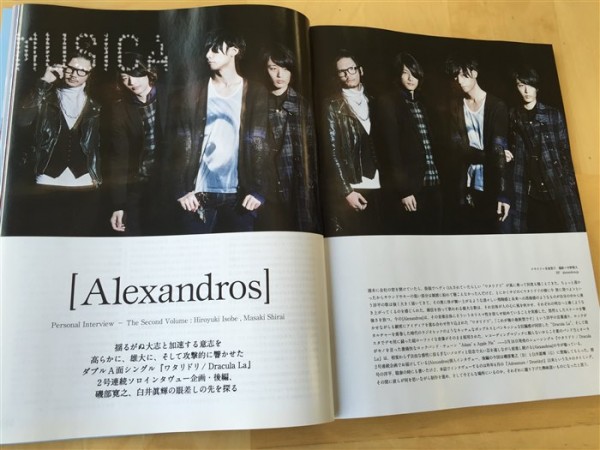SUPER BEAVER、
あなたがあなたを愛するための最高作『愛する』
――眩い光を放つ愛のロック、ここに放たれる

たとえばこの世に俺ひとりしかいなければ、孤独や寂しさもないし、
生きていて起こるすべてのことも、誰かがいるから成り立つことで。
個性や「らしさ」以前の話で、
人に認識されて初めて自分なんだって、わかったんだよ
『MUSICA 4月号 Vol.96』P.94より掲載
■お世辞抜きで、大傑作だと思いました。
柳沢亮太(G)「お! ありがとうございます」
■本当にデカい作品だと思いました。歌と曲のすべてに、聴く人を真正面から受け止めていく強さとキャパシティがあって。『愛する』っていうタイトルにも、これまでの道が全部結実したことが表れてると思うんですけど。
渋谷龍太(Vo)「今まで、自分達で『節目』みたいなものを意識したことはなかったんだけど――今年で10周年っていうタイミングに不思議とピッタリくるような、『今までやってきたことが全部繋がったな』っていう感触が凄くある作品になったと思います。録ってる最中はそういう意識はなかったけど、改めて振り返ると、そういう作品になったなって」
■逆に言うと、「元々、自分達はこういうことを歌いたくてやってきたんだろうな」とか、「今まで歌ってきたことの一番根底にある想いはこういうことだったんだろうな」とか、そういう感触があったということ?
渋谷「ああ、その感触は、前作の『らしさ』の時に既にあったことなんだよね。凄く明確に『これだ!』っていうのがドハマりしたし、あなたの存在そのものがあなたらしさだって――『世の中の人がみんながこうあったら、一番素敵だな』っていうことをハッキリと曲にできた実感が凄くあって。バンド人生で一番ピンときた曲というか、10中の10がハマった感じがあったんだよね。その“らしさ”が基盤になって生まれてきた作品だと思うから、凄く自然で、凄く真っ直ぐに臨めた作品なんだよね」
柳沢「そうだね。それと、全体としてデカいスケールのあるアルバムっていうのは、確かにそうなったなって思う。言葉だけじゃなくサウンドの表し方的にも大きなものにしていくっていうのは、『あなたに歌ってるんだ』っていうことを明確なテーマにした『361°』くらいから考えてたし。あとは、バンドとしても個人的にもいろいろあった2014年も大きかったと思う。……別に、いろんなものを狙って音楽に付随させようとしてるわけじゃないけど、その全部のタイミングが不思議と合ったのかな。このバンドが始まって、いろんなタイミングで歌ってきたことが伏線になって、それを意図せずとも回収し切った作品だと思う」
■意図せずとも伏線を回収し切ったっていうのは、その時に自分達が歌い鳴らして伝えてきたことがちゃんとひとつの線で繋がっていたっていうことに気づけて、自分の中で腑に落ちたっていう感じなの?
柳沢「たとえば『361°』で歌った“ありがとう”だったり、“らしさ”だったりを聴いてから今回のアルバムに戻ってきてみると、凄く全部繋がってるし、大きく言えば、俺達の歌いたいことはそんなに変わらないんだなっていうことに気づけて。それが今作のタイトルの『愛する』っていう言葉に限るんだっていうことだったんだよね。たとえば人の本音を突くようなことを歌いたくなった時期があったのも、自分達自身が思ったように生きられなかったり、思ったようにバンドを愛せなかったりした時期を経験してきたからで。……20歳前後の頃に何がキツかったって、メジャー時代に自分達自身を疑ってしまっていたことや、自分達自身のことが好きじゃなかったっていうことで。そこから2012年に自分達でレーベルを始めて、自分達の音楽を取り戻していって、それで今のチームと出会ったりして――自分達で自分達を疑っていたところが始まりだったから、そこから積み重ねると、きっと結論はこういう『愛する』っていう言葉になるんだなって思ったんだよ。……だから逆に言うと、ようやく自分達を愛して、信じられるようになってきたんだよね。『自分はこうなりたいんだ』っていう理想を追いかけていく時に、単なるイメージだけなのと、何故それが理想なのか?っていうことを理想の正反対を知った上で話すのとでは、説得力が違って。で、俺達は図らずも、理想の反対の自分達を一番最初に経験したからこそ、『愛する』っていうタイトルになったんだと思う」
■じゃあ、柳沢くんが「この作品にとって、2014年にいろいろあったのもタイミングとして大きかった」って言ったのは、どういうことだったの?
柳沢「……俺が昨年の9月に突然体調を大きく崩してしまって、入院したんだよね。1ヵ月入院生活を送って、さらにそこからリハビリも含めて休養して、ようやくライヴに復帰できたのが11月の末だったんだけど」
■これは今だから訊くけど、体調を崩したっていうのは、どれくらいのレベルの病気だったんですか?
柳沢「……今まではまったく言わなかったけど、病気のレベルとしては、生死を彷徨うくらいのものだったんだよね。意識が飛ぶことはなかったし、9月は『らしさ/わたくしごと』のリリースもあったから『入院なんて無理です』って言ったんだけど、調べてもらったら、本当に生きるか死ぬかギリギリの重い症状で。ただ、メンバーにもスタッフにも唯一お願いしたのは、『とにかくSUPER BEAVERの活動を止めないでくれ』っていうことで、メンバーもスタッフも『絶対に活動を止めない』って腹を決めてくれてたんだよね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 矢島大地
『MUSICA4月号 Vol.96』