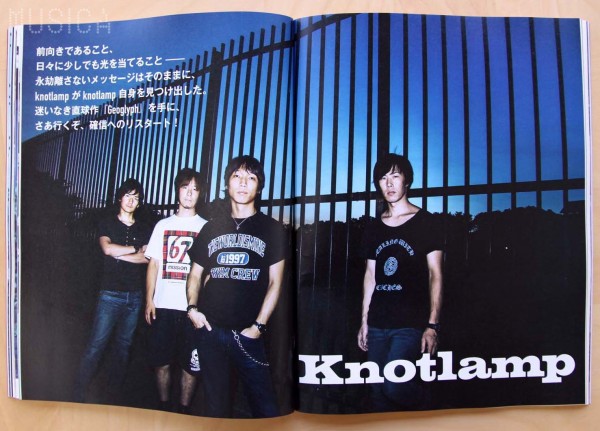SILLYTHING、『cross wizard』リリース記念企画鼎談:成田大致(SILLYTHING)×夢眠ねむ(でんぱ組.inc)×玉屋2060%(Wienners)
キャラとキャラがぶつかり合い、
好奇と珍奇がもんどり打つ!
ロックの固定概念を軽やかに飛び越える
驚異の異種格闘大鼎談
『MUSICA 10月号 Vol.66』P110に掲載
■今回のSILLYTHINGのアルバムが、アニソンやアイドル系のコンポーザーを中心に、ミュージシャンから声優、漫画家、プロレスラーまで、本当にたくさんのゲストを招いて作ったものになっていて。今のシーンの中でこの作品がどういう意味を持ってるのか、この3人の鼎談の中で明らかにできればと思ってます。よろしくお願いします。
一同「よろしくお願いします」
■玉屋さんは今作を聴いて、どう思いました?
玉屋2060%(Wienners)「聴いてみて『あ、今の時代の人が鳴らしてる音だなぁ』って感じましたね。リアルタイムの今の人達だなって感じがしました。僕らも雑食は雑食なんですけど、パンク~ハードコアの雑食とか、ポップスの雑食とか、アニソンの雑食とか、雑食にもいろんなのがあって面白いな!ってことを凄く感じましたね」
■その辺り、そもそもどういうコンセプトでこういう作品を作ろうと思ったのか、成田さんから改めて話してもらえますか?
成田大致「まぁ、前のバンドが、いわゆる単純なロックンロールバンドみたいなやつをやってたんですよ。なんですけど、もっと自分自身に近いものがやりたくなったからやめて。かつ、やるんだったら誰も聴いたことがない新しいロックがやりたいっていうことだったんですけど。最初は、楽曲提供をひとり入れようっていう考えからこのプロジェクトは始まったんですよ。で、気がついてみたら、こんなになってたんですけど(笑)」
夢眠ねむ(でんぱ組.inc)「じゃあ、最初からいろんな人と全コラボする予定ではなかったんだ?」
成田「最初は1曲だけのつもりで、今一番面白い曲を作ってる人達はアニソンやアイドルの楽曲を制作している人達だと思うし、そういう人達とアルバムを作ったら全曲キラーチューンのバンドにすることができるんじゃないかって――たとえばWiennersさんもでんぱ組.incさんもキラーチューンだけのバンドだと俺は思ってるんですけど」
夢眠「うわ! めっちゃいいこと言いますね!」
玉屋「嬉しいっす、嬉しいっす」
成田「SILLYTHINGもそういうキラーチューンだけのバンドになりたいっていうところで、楽曲提供してもらうアルバムを作りたいっていう。やっぱり今って、どっちかって言うと曲単位になってるじゃないですか。そういう感じのアルバムを作りたくて――」
(続きは本誌をチェック!)
text by 寺田宏幸
『MUSICA 10月号 Vol.66』のご購入はこちら