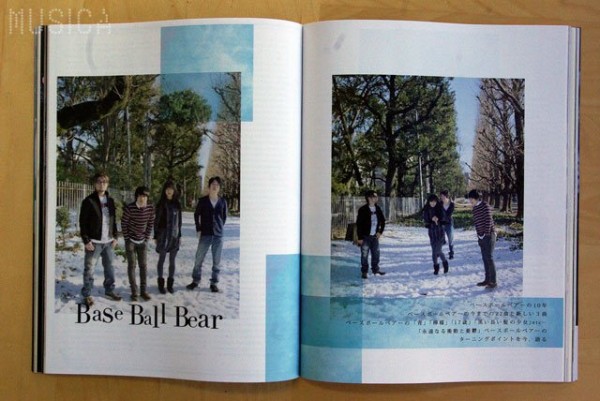KNOCK OUT MONKEY、生々しい感情が滾る『reality & liberty』堂々完成
己の深層にある言葉を曝け出し
一層ラウドに、一層鋭利にぶっ放す音塊――
いよいよ心の深奥を開陳した暴れ猿の
本当の自由へ向かう闘いは、ここからだ
『MUSICA 3月号 Vol.71』P108に掲載
■前作『0 → Future』で見せた多様なジャンルのミックス感から進んで、音のハードさや各要素の強度を振り切らせた作品だと感じました。
「そうですね。前回は、『いろんな武器があるよ』って、たくさん武器を作った感じがあったんです。ピストルでも刀でもいけますよっていう。その1個1個の強度を高めた感じがするし、曲と向き合う行為が今回のほうが濃かったと思います。前回はやりたいことが凄く多くて。それを一度詰め込んで、すべて吐き出してから次を考えようっていう感覚だったんです。そのツアーもやりながら制作したから、現在進行形の作品ができましたね」
■曲に向き合う時間が濃かったっていうのは、技術的なことだったんですか? 精神的なこと?
「『0 → Future』をリリースしてからフェスに出たり、ツアーの中でも、僕らをあまり知らないお客さんも集まって盛り上がってくれたり、そういうのは今までになかったことだったんです。それで一気にいろんな情報がワッときて、それを咀嚼していくのに時間がかかったというか。たとえば『フェスに出た次の日に曲を書きましょう』っていう時に現実感がなくなってしまったりとか。そういうスイッチングが多かったんです」
■日常生活と、グッとアガってるライヴの間のスイッチングって、自分のテンションの上下や生活の波とか、精神面の落差とかを正面から見つめるような感じだったんですか?
「そうですね。でも、その感覚がないと曲ができないっていうのは自分でわかっていて。フェスの翌日に目覚めた時、一気に現実に戻ってるわけじゃないですか。寂しいと思う部分もあるし、それが『もう一回出てやるぞ』っていう想いにもなったし。逆に『あの日は楽しかったのに』って落ちる時もあったりして。1日の感覚が全然違ったから、今回は浮き沈みが多かったかもしれない。聴いてみると本音を曝しまくってると思って(笑)」
■今回の『reality & liberty』は、音楽性に変貌があるわけではないけど、変化作だと感じたんです。おっしゃったように、w-shunさんが音楽に注ぐ感情の振れ幅が凄く大きくなってる気がして。
「ああ、そうですね。不特定多数の人が自分達の音楽を聴いていて、そこで聴く人の感情を全部読み取れなくても、もっと自分の根っこを見つめて感受性豊かに日常を見られるようになれば、自分以外の人のこともわかるようになるんじゃないかなって思ったんです。もっと自分達の言葉や、スタイルや、人間性の根っこに向かって掘っていこうっていう感覚で。その中でできた曲達だから、言葉選びも前回とは違うと思う。自分がステージで言葉を吐く時に『人間ひとりのことですら完璧にわからないのに、何百人、何千人のことなんてわかるわけない』って思ってる部分はあって。……人ってわからないものだとは思うんですよ。凄く複雑ですよね。だからこそ、その中で引っ掛かる、シンプルで単純なキーワードを探したいって思ったんです」
(続きは本誌をチェック!)
text by 矢島大地
『MUSICA 3月号 Vol.71』のご購入はこちら