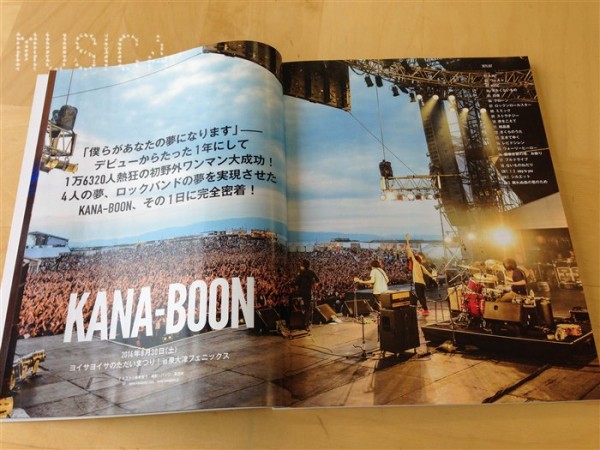神聖かまってちゃん、音楽的達成と転換期の葛藤の間で
の子が揺れる

過去の自分はもういないんです。今の自分しかいないんです。
思い出っていうものはあるかもしれないですけど、
今の自分をいかに見つめて鍛えて飢餓感を持って次のことをやれるか。
それしかないですよね
『MUSICA 10月号 Vol.90』P.106より掲載
■本当に、素晴らしい作品がっ!
「ははははは、なんですかその始まり?(笑)」
■いや(笑)。今回のアルバムは名曲の揃いっぷりもそうだけど、バンドの演奏含めて今までよりも格段に音楽的完成度の高い作品に仕上がってて。
「まぁこのアルバムの出来っていうのは、神聖かまってちゃんとして、4人だけじゃなくサポートの人やエンジニアさんも含めたチームとして、一歩一歩完成していってる過程が出てると思います。まだゴールじゃないですけど、でも今のライヴの出来もかなり完成されてますし」
■の子くんにとっては長年の間、バンドでレコーディングすると自分のデモの世界観通りにならないっていうのが最大の葛藤だったわけじゃないですか。でも、今回こそはピタッとハマッた感があるんじゃないかなと。
「ピタッとでもないですけどね。でもなんだかんだ、このアルバムができた時は、今まで以上にピタッとハマッてるっていうのは感じました。とはいえデモのほうがいいっていうのは相変わらずありますけどね」
■そうなんだ。の子くん的にも今回こそは音楽的に満足が行く作品になったんじゃないかと思ったんだけど。
「音楽的にはそうですね。音楽的にはスキルが上がってレベルアップ感はあります。そこは感じてます。けど……満足かって言ったら満足ではない。まぁ満足じゃないもん出すなって前から言われますけど(笑)。けど、ほんとのこと言うとそうなんだよな。もちろんマスタリングした時は当然満足してますよ。でも時間経って聴くとまた違うじゃないですか」
■まぁ多くのアーティストは作品を作り終わって時間が経つと、ここはもっとこうできたのにな、とか出てくるものですよね。
「そうですね。だから僕の場合、これは70点とか」
■の子くんにとっては、このアルバムはどういう作品なんですか?
「アルバム単位で言うと、最初は打ち込み寄りにしたいっていう意見を持っていったんですよ。それは楽曲が打ち込みに寄ったという部分と、そもそも僕は打ち込みな人間なんで。言ったらもう、ベースとドラムも完全に打ち込みでいいんじゃねぇか!くらいの人間なんで」
■でも実際は、打ち込みの強い曲とバンドサウンドの曲と、バランスよく入ったアルバムになってるよね。
「はい。やっぱそんなこと言っちゃったら元も子もないじゃないですか。『今回のアルバムは打ち込みを全面に出したいからおまえら休んでろ』とか言ったらメンバー絶対辞めちゃうんで。で、そこを上手くまとめてくれるのがエンジニアの(萩谷)真紀夫さんで、『じゃあ打ち込みとバンドを上手くまとめて』っていう案を出してくれたんです」
■なるほど。でも、そこに対してメンバーも頑張りましたよね。バンドの演奏が上手く行っているというのは、の子くんも感じてるんでしょう?
「はい。正直そこは本当に進歩したとは思ってます」
■去年の子くんが自分のソロで神聖かまってちゃんの曲を違うメンバーとセルフカヴァーするという斬新な手段に出て、しかもライヴも含めて素晴らしい音楽作品を作って。ただ、あれはメンバーからしたら屈辱的だったと思うんだよね。だって、自分達の演奏と比べざるを得ないし、その差ははっきりと提示されちゃったわけじゃないですか。
「まあ、そういう目的もありましたからね」
■やっぱあったんだ。
「ありました、当然ですよ」
■もの凄い荒療治だけど、それは功を奏したのかもしれないね。
「そうですね。だからメンバーはメンバーで、いろんな闘い、葛藤があると思います。僕に対すること然り、それぞれの人生然り………まぁでも、その演奏面での進歩っていうのは、年季がモノを言ってるだけだと思うんですよ。やっぱりもう何枚も作ってきて、レコーディングの仕方もいい加減に学びましたしね。ウチら最初は何も知らなかったですから。それがエンジニアの真紀夫さんとかサポートの人の力もあってようやくまとまったというか。だから断じて4人の力だけではないんですよ」
■相変わらず手厳しいね。でも年季やサポートの力はあれど、そもそもの4人が音楽的にちゃんと成長できてる感じがするけどな。
「ま、大人になってるんじゃないですかね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 有泉智子
『MUSICA10月号 Vol.90』