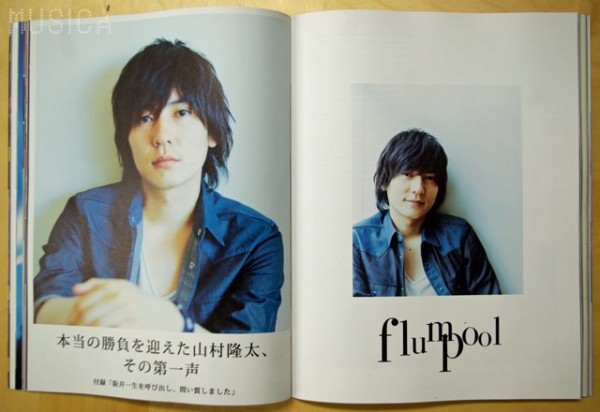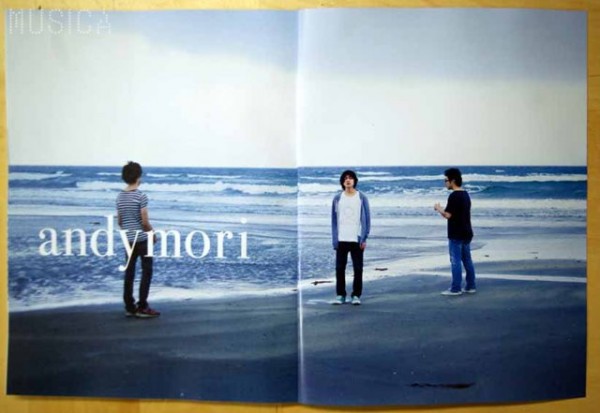星野源、療養のための一時活動休止によせて
先ほど星野源のオフィシャルサイトから、
療養のための一時活動休止と、
それに伴い、7月19日に日本武道館で予定されていた
「星野源ワンマンライブ”STRANGER IN BUDOKAN”」公演の延期、
そして6月29日にビルボードライブ東京で予定されていた
「星野 源 “moment”」公演の中止が発表されました。
なお、武道館の延期日程に関しては、現在調整中だという旨が記されています。
昨年12月にくも膜下出血で倒れた後、
『Stranger』をちゃんと完成させてリリースし、
そしてこの初の武道館公演を成功させるために
星野さんがどれだけの想いと気力をもって取り組んできたのか。
取材を通してその姿を目の当たりにさせてもらってきただけに、
今回のことは、正直、言葉が見つかりません。
ただ、ひとつだけ。
早い段階で状況がわかって治療に入ることができて、よかった。
無念な気持ちとか、なぜ星野さんにこんなことがとか、
いろいろ思ってやるせない気持ちでいっぱいだけど、
そして星野さん自身のほうがそういう想いでいっぱいだろうけど、
でも、やっぱり、
大事に至る前に療養に入ることができてよかった、
またあんなことにならずによかったと、
心から思います。
だから星野さん、ゆっくり休んでください。
ゆっくり治してください。
いっぱい思うことはあるでしょう。
私には星野さんの心境がわかるなんてとても言えない。
だけど、どうか、じっくりと治療に専念してください。
いつかと同じ言葉になっちゃうけれど、
やっぱりこの言葉以外にないなと思うので、また同じことを言わせてください。
星野さん、愛を込めて、待っています。
いつまででも、待っています。
『Stranger』や『ギャグ』をはじめとする、
たくさんの星野さんの音楽を聴きながら、
ずっとずっと待っています。
なお、MUSICAの連載「精なる日々」は、
今出ている最新号(7月号)の掲載をもって、一度ストップします。
現段階では、今後どのような形になるのかは未定ですが、
ただ、星野さんが復帰した暁には
必ずまた何か一緒にやっていこうと思っています。
その日まで、どうか焦らずゆっくりと。(有泉智子)