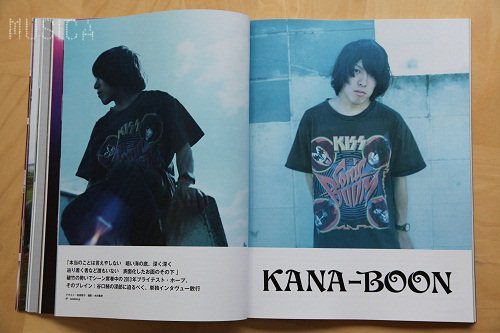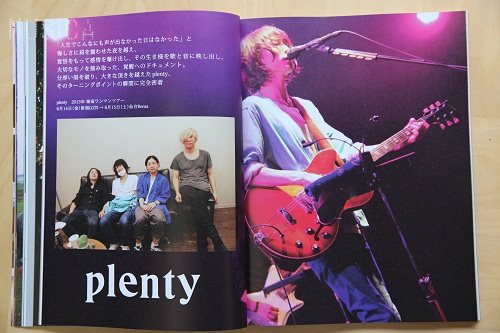a flood of circle、新アルバム『I’M FREE』で見せた理屈抜きのロックンロール

俺の居場所はロックンロールだけ――
逆風と変化に晒され続けたAFOCが
初めて手に入れた安堵と平静の中で、
ただその確信だけを頼りに作り上げたニューアルバム『I’M FREE』。
理屈もへったくれもなし、泰然自若のぶっ太いロックを
その耳で、その心と身体で受け止めよ
『MUSICA 8月号 Vol.76』P.82より掲載
■今回は、本当になんの理屈もなく、ただのロックンロールアルバムだと思って聴かせてもらって。ただのロックンロールナンバーが12曲入ってるだけのアルバムだと。
「あははは、それ、どうなんですかね」
■いや、これはもの凄く褒め言葉のつもりで言ってるんですけど。
「めっちゃネガティヴワードだと思った(笑)」
■(笑)でも、これまでメンバーの入れ替わりとかバンドを取り巻く状況とかいろんな物語があって、その度に今思ってることっていうのをテーマとして掲げてアルバムを作ってきたと思うんだけど、今回はそういう理屈やテーマを抜きにしてやりたいことをやり切った作品なのかなっていう気がしていて。
「あぁ、そうですね。そういう気持ちよさはありますね。今必要だなと思うアルバム、一番聴きたいアルバムができたし。再生回数的にも、今までで一番自分でも聴いてるし」
■自分でもやり切れた充実感や満足感を感じてるんだ?
「そうですね。場所とか人とかを選ばないで、遠くまで飛ぶアルバムにしたかったんですよ。『LOVE IS LIKE A ROCK’N’ROLL』の時は震災の後の反射神経で<LOVE>が出てきて、次のミニアルバムは何故か<FUCK>まで行っちゃったんですけど、その時は震災から時間が経てば経つほど、自分が社会の中で何かしなきゃいけないんじゃないか?って強迫観念のようなものを凄く周りに感じてて――まぁバンドマンだけかどうかわからないですけど、俺はそれを突破する曲を書きたくて“FUCK FOREVER”を書いたんです」
■うん。よくも悪くも、バンドを取り巻く環境とか、今の世の中に自分達が何を鳴らせるのかっていう役割意識とか、そういうものを常に意識してましたよね。
「でも、今回はバンドが初めて2年半続いたっていうのもあったし、ちゃんとじっくりメッセージを作ったりメロディを作ったりするアルバムにしたくて。もっと人に歌を聴いて欲しいっていう気持ちが強かったんですよね。反射神経とかだけじゃなくて作れるもんがあるんじゃないかって」
(続きは本誌をチェック!)
text by 寺田 宏幸
『MUSICA 8月号 Vol.76』より