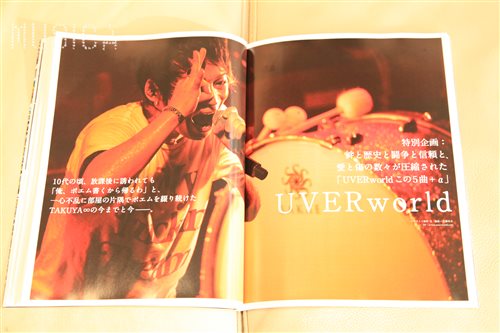ACIDMAN、久しぶりのシングルと共に
再出発への想いと覚悟を語る

今我々は空を見て、宇宙を目指して、
これからきっともっと上を目指すんですよね。
これって昔から受け継いだ、どこかにインプットされた記憶だと思うんです。
それを俺は命と呼ぼうと思って
『MUSICA 5月号 Vol.85』P.120より掲載
■(唐突に)大木って、STAP細胞の一連のニュースとか見てて、「あ、こういうことね」みたいに体系立てれる知識を持ってるんだ?
「STAP細胞は、結局まだわからないですけどね。でも、iPS細胞とかは何年も前から言われてたものですよ。熟知はしてないですけど、一般の方よりは知ってますね」
■あのニュース見る度に、大木のことを思い出すんだよね。
「あはははははははは! だからもう、俺は音楽じゃなくても全然いいんですよね、きっと(笑)。たまたま音楽が好きで、バンドが好きでやってて、『さあ、何を書くか』って言った時に、一番好きなものを書かざるを得なかったというだけだと思うんですけどね。で、いまだにやっぱりそれが大好きで」
■では始めましょう。凄くご無沙汰なんですが。お休みしていたんですか?
「いや(笑)、普通にいつも通り、いつも以上にペースを上げて制作してましたね。(事務所が)独立したっていうのもあって、時間は前作から空いてるんですけど、ほとんど休みなく作ってました」
■シングルのリリースとして考えていくと、1年半弱ぶり、アルバムの『新世界』から1年2ヶ月ぶり。これはやはり独立して、自分達の体制を1から作り直したことが大きかったの?
「いや、それはそこまで関係してないですね。曲を作り、ツアーもやり、そしてまた曲を作っての時間の流れで、今のタイミングになったと思うんですよね」
■毎回アルバム後のシングルっていうのは、次のアルバムを見据えて作ってるよね。
「そうです、そうです。基本的に1個のアルバムのレコーディングが終わったすぐ何日か後に、必ずスタジオに籠るんですよ」
■休みたいじゃん。
「もう、1日休むだけで嫌になるんですよね」
■牛角とか行きたいじゃん。
「休みの日に牛角っすか!? 牛角は普段も行けるじゃない(笑)」
■いや、創作とかしてるとさ、ゆっくり焼肉も焼けないでしょ。
「いや(笑)、でもそれが日常なので、全然大丈夫です。それでしばらく曲作りに入って、ある程度の曲数が見えて、2~30曲見えたぐらいでふたり(さとま&いちご)に聴かせるっていう」
■アルバムを作った直後に、間髪入れずに2~30曲作って、独特のラヴレターを渡されるメンバーの気持ちはどうなんだろうね。
「はははは、複雑かもしれないですね。でも作りたいものができてしまって、アルバムが出るまで待てない、もっと早くやりたいって思って。……足りないんですよね、1枚だけだと。足りないから、もっと違うことをやりたいなと思って。世に出ることが巣立ちじゃなくて、俺の中ではレコーディングが終わった時に巣立ちなんですよね。だから、でき上がったアルバムに対しては『もう自由にやってくれ』と。『もうハタチを超えたんだから』っていう感覚になって」
■では、時節を追っていろいろ訊いていこうと思うんですが。まず、『新世界』がリリースされました。そこからアルバムが出るまで何ヵ月間かあったと思うんですけど、その間に事務所を移籍独立して、自分らでやってくというスタンスを取ったんですが。そこに至る経緯を教えてください。
「ずっと長いこと、デビューちょっと前からお世話になってた会社があるんですけど、自分達のこれからのミュージシャンとしての生き様って、事務所に守られてどうのこうのっていうんじゃなくて、ちゃんとお金のことも含めて、責任あることをやっていかなきゃいけないなって、ずっと前から思ってたことで。それがやっとこのタイミングって感じでしたね。3人の息も揃っているので、ちょうど今の時期が一番いいんじゃないかっていう――アルバムのタイトルも『新世界』だったしね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 鹿野 淳
『MUSICA5月号 Vol.85』