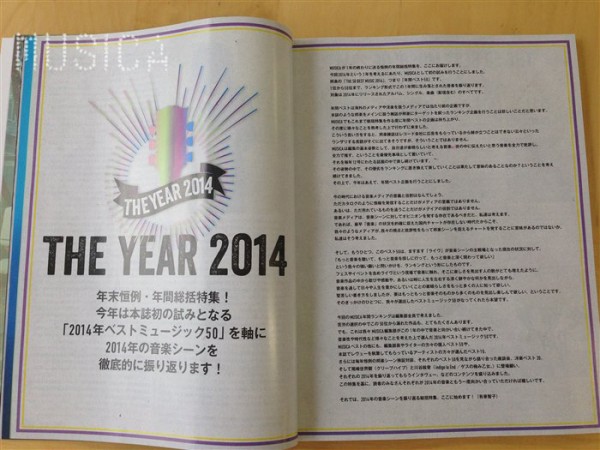cero、明らかな新機軸と
進化を刻むシングル『Orphans/夜去』で
特異なるバンドの立ち位置と通底する思想を紐解く

ブラックミュージックとか魔術的なものを
都市型に押し込めたのがシティポップだけど、
実はそこからはみ出てくるものを、
もうひとつ大きいところで見てみたいんです
『MUSICA 1月号 Vol.93』P.112より掲載
■前回のシングル『Yellow Magus』がちょうど1年前になるんですけど。あの時のソウル色とかブラックミュージック色が引き継がれつつ、もっと甘くてメロウなサウンドが鳴ってるシングルで。
高城晶平(Vo&G&Flute)「そうですね。『Yellow Magus』を去年の年末に出して、今年の始めから新曲をバンバン作っていこうということで、3回ぐらい合宿をやりまして。合宿っつうか、厳密に言うと、本当に寝泊りして合宿したのは1回だけなんですけど。近所のスタジオに曲を持ち寄って、3日間ぐらいガッツリ時間を取ってロックアウトでずっとやる、みたいな。そういう感じで曲作りが始まって、『これはシングルとしていいんじゃないか?』って選ばれたのが、この“Orphans”と“夜去”だったんですよね」
■そもそも今までそうやって合宿形式で曲作ったりしてたんでしたっけ?
高城「いや、こういう作り方は初めてですね。思うんですけど、普通のバンドって、ファーストアルバム、セカンドアルバムくらいまでは下積みのストック、プラス書き下ろしの何曲かでやれるところがあるじゃないですか。で、サードくらいからストックがなくなってきて、真のファースト的な感じになっていくみたいな。まさに俺らもそれで。これまでのストックをだいぶ使ったし、割とクリーンな状態で1から作品を作ろうっていうことで、みんなであーだこーだやってみようって。初めてですね、こうやって合宿で曲を集めて作るっていうのは」
■初めてやってみてどうでした?
高城「面白かったよね?」
荒内佑(Key&B&Sampler)「うん」
高城「家で作ってきたデモの段階で、割と設計図がしっかりした状態で持っていくから、続々と集まっていくのが楽しいなって。体育会系の合宿とか、そういう感じではないんです(笑)」
橋本翼(G&Cl)「逆にダラダラできるから、それが向いてるっていうか。時間を贅沢に使ったっていう感じですね」
高城「あぁ、そうだね。あと、“Orphans”は、はしもっちゃんが歌詞なしの状態で持ってきたりして。1日目は、とりあえず歌詞はついてないけど、見切り発車で演奏だけやっとこうか?みたいな感じだったんですよ。で、その日は1回家に帰って、僕が『そういえば、これに合いそうな歌詞が自分のストックの中にあったな』って思って、次の日に『実は歌詞を乗っけました』ってやれたんですよ。『明日もあるから、じゃあ明日までに書いちゃおう』と思ってさーっと書いて持ってきたりもできたし、3日間の中で動きがあることができたっていう意味でも合宿はよかったですね」
荒内「基本的に締め切りがないと曲が作れないからね(笑)。断片とか、何かしらのストックは常にいっぱいあるんですよ。けど、合宿があることで、それを1個1個形にしていこうっていうきっかけになるので」
■じゃあ今回、“Orphans”は初めて橋本さんがceroに持ち込んだ曲になるわけですけど、そうやって合宿で全員が曲を持ち寄る中でこれは自然の流れだったんですか?
橋本「そうですね。今回は合宿で曲を提出するムードがあったんで――」
高城&荒内「ははははははははは!」
橋本「宿題があったんですよね(笑)」
高城「確かにね。『ひとり1曲出そう』っていうコンペ的な合宿だったんで、『はしもっちゃんも出そうよ』みたいな(笑)」
■それって、橋本さん的にはプレッシャーだったりもしたの?
橋本「そうですね。今までなかったから、どうなのかな?って思ってたんですけど……タイミングがよかったんですよね。それでもまだかなりポップ寄りではあるんですけど、バンドのやりたい音楽と一致したっていうか。実はトラック自体は結構昔からあったやつで、ずっと放置してたんですけど、その間に聴いてた音楽に影響を受けて、混ぜてみたらいい感じになるんじゃないかなって思って提出したんです」
■ちなみに、その昔の段階のものもみんなに聴かせてはいたの?
橋本「昔送ったよね?」
高城「うん。『そういえば前に聴いてたな』って思って。5年前ぐらい。『あれ、“Orphans”だったんだ?』って。その時は形にならなかったんですけど、5年経ってちょうど自分達のモードとも合致するところがあって、上手いことこのタイミングで形になりましたね」
橋本「その時とはちょっと違うんですけどね。前のは今回のデモほど作りこまれてない感じでした」
荒内「クラ(クラリネット)が入ってたよね」
高城「今のアレンジほどストイックっていうか、音数の少ないカラッとした感じではなかったかな。もうちょっと可愛い、ポップな感じだったよね。今はそれよりクールっていうか、少し冷めた感じになりましたね」
荒内「ビタースウィートだよね。『Yellow Magus』以降の楽曲群は、いわゆる今のプログレッシヴ・ジャズみたいなものの影響があって、言ってみればちょっとマニアックなものが多いというか。音源だけ聴いてる人にとって『My Lost City』 と次のアルバムに断絶を感じるかもしれない。そこは実は地続きなんだよっていう連続性がちょっと見えづらいと思うんだけど、“Orphans”はその中間でちょうどいいっていうか」
高城「そうそう。今作ってるアルバムの断片になっていくようなピース――多様な曲があって、ライヴに足繁く通ってる人はこれまでのceroと『Yellow Magus』、そこから先の流れがだんだん見えてきてると思いますけど、音源だけ聴いてると、曲によっては『ガラッと変わっちゃったな』って不安になるかなって思って。そういう意味でも、“Orphans”と“夜去”はちょうどよかったんですよ。今の自分達とかつての作品群の間をつなぐ橋渡し的な要素も持ってるなって思って。お客さんと足並みを揃えるっていう意味でも、ここでシングルを切っておいてよかったなっていう感じがしてますね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 寺田宏幸
『MUSICA1月号 Vol.93』