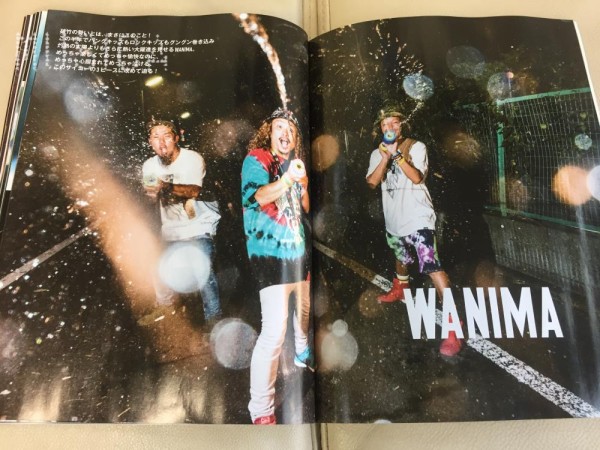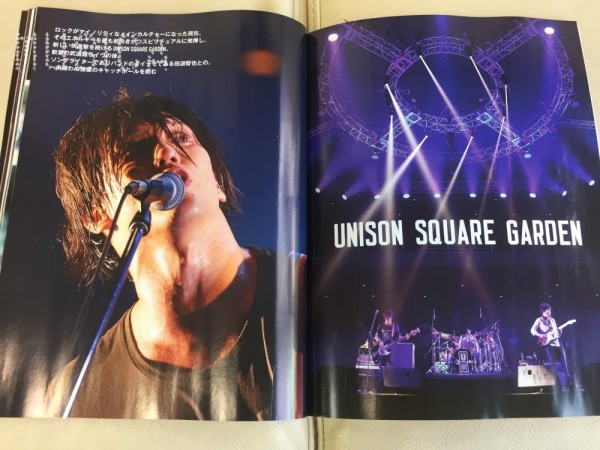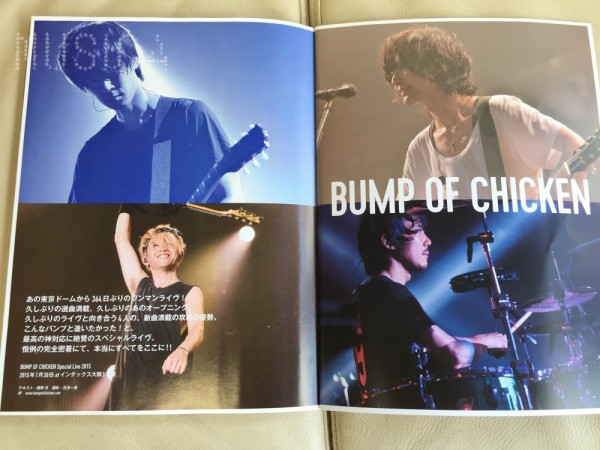04 Limited Sazabys、
地元名古屋・Diamond Hallでのツアーファイナルに完全密着!!

一気にシーンの主役筆頭へと躍り出たフォーリミ。
メロディックパンクシーンを越えて膨らみ続ける熱狂と
めまぐるしく変わりゆく景色のど真ん中で
決して変わらぬバンドの青春を鳴らした、「CAVU tour」
地元名古屋でのファイナルに密着!
天衣無縫に駆けながらも確実に射程に捉えた「次の大海原」を紐解く! 語り合う!
『MUSICA 9月号 Vol.101』P.66より掲載
(前半略)
7月17日(金) 名古屋・DIAMOND HALL
前日から本州に上陸していた台風が北上している中、ギリギリのところで直撃を免れた名古屋。時折強めの雨こそ降るものの、ライヴに支障はなさそうだ。そう安心していると、まずはメンバー入り予定の12時半にRYU-TAとHIROKAZ、続いてKOUHEIが到着し、早速3人で昼食。このDIAMOND HALLには楽屋がふたつあって、エントランスから奥の広い部屋がメンバー用、手前の小さな部屋がスタッフの荷物置き場になっていたのだが、何故か3人ともスタッフルームで弁当を広げている。そこに入れ替わり立ち代わりライヴスタッフが入ってきては、3人との会話を楽しんでまた仕事へ戻っていく。わざわざスタッフルームで飯を食べるメンバー、わざわざそこに言葉を交わしにくるスタッフ。その感じが、このツアーでどれだけの絆や信頼をチームとして築けたのかを表していて、とてもいい空気である。ちなみにGENは大遅刻で結局14時に会場に入り、遅刻をからかわれながら弁当を食う。RYU-TAが言うには「ま、あいつの寝坊はデフォルトなんで(笑)」とのことだが、GENに言わせると、乗ったタクシーの運転手が悪かったらしい――どちらにせよ、1日の始まりがめちゃくちゃのんびりだ。
14時を過ぎた頃、ステージでKOUHEI、RYU-TA、HIROKAZがサウンドチェックを始めると、GENが、ここ最近使っていなかったバンド結成時のベースを持ってきた。「今日は地元なんで初期からのお客さんもたくさん来てくれるだろうし、バンド結成したばっかりの時は、それこそ『DIAMOND HALLでやれたらいいね』って言いながらライヴ観に来て暴れてたんです。だから、“Standing here”(『Marking all!!!』)とか、懐かしい曲をこれで弾きたくて。音はよくないっすけど(笑)」と話す。GENはライヴの時にいつも「名古屋の04 Limited Sazabysです」と自己紹介するが、それはきっと、GENが話してくれたような音楽の原風景や憧憬や衝動を忘れないためなのだろうし、彼らの場合、それが音楽にあまりに鮮やかに映るところがいいのだ。そこで感じたことはリハーサルを見ていても同じで、5~6曲のブロックを後半からなぞっていき、サウンドチェックが綿密だった分スムーズなリハだな――と思ってたら、“teleport”の辺りで、4人とイベンター、マネージャー、ステージスタッフがRYU-TAを囲んで大真面目に話し合っている。するとRYU-TAは会場の導線を確認しながらステージ裏を移動、2階席まで駆け上がっていった。これは何だ?
RYU-TA「間奏で姿を消して、裏導線を通って2階席に現れるという……“teleport”です(笑)」
……そういうことか。そして最終的に、2時間みっちりなリハーサルの中で最も時間をかけたのが、この瞬間移動(?)についてだった。たとえ傍から見れば一瞬でも、下らなくても、面白いと思えば全力でやるし、それをやるのがロックバンドなんだ――そういう音楽であり、バンドであり、チームなのである。こういう「全力の遊び心」が、このバンドの痛快なところなのだ。
(続きは本誌をチェック!)
text by矢島大地
『MUSICA9月号 Vol.101』