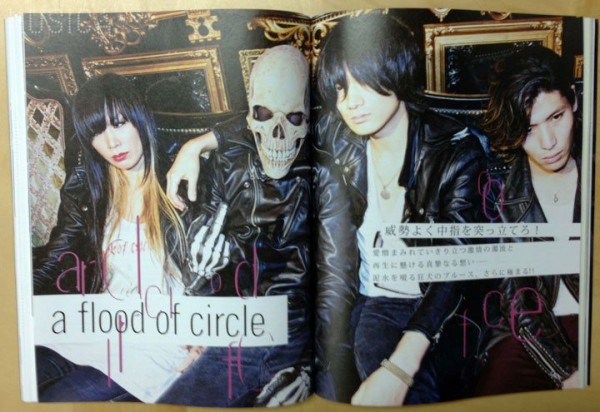スペースシャワー列伝JAPAN TOUR2013開催記念対談! 前編・中嶋イッキュウ(tricot)×金廣真悟(グッドモーニングアメリカ)
恒例!シーン中枢への登竜門「列伝TOUR」出演バンドの対談2連射!
第1弾はtricotの中嶋イッキュウと、グッドモーニングアメリカの金廣真悟。
音像は真逆ながら、同じく強き表現者であるふたりを迎撃!
『MUSICA 1月号 Vol.69』P116に掲載
■両バンドは、これまであまり一緒にやる機会はなかったと思うんですが――。
中嶋イッキュウ(tricot/Vo&G)「そうですね、(対バンしたのは)1回だけですよね?」
金廣真悟(グッドモーニングアメリカ/Vo&G)「うん、それこそ、スペシャ列伝のイベントで」
■ではまず、お互いの音楽性に対して、どんな印象を持っているのかから教えてください。
金廣「『女性のバンドでこういう音楽やるんだ?』っていうのが第一印象ですね。たとえば最近のガールズバンドっていうと、チャットモンチーだったり、ねごとだったりというイメージがある中で、(tricotは)アンダーグラウンドで複雑な匂いがあって、音も凄くゴリゴリしていて。対バンする前から周りのバンドマンからも『tricotカッコいい』って聞いてたんで、『カッコいい女性バンドってどんな感じだろう?』って思いながら観てたんですけど、『いいところ攻めてるなぁ!』って思いましたね」
イッキュウ「私はグッドモーニングアメリカって自分らとは真逆というか、凄いストレートやと思ってて。ストレートにやるのって、逆に難しいと思うんですよ、頭ひとつ抜けるのが。でも“空ばかり見ていた”のサビとか凄いなぁと思って。あと、初めて聴いた時に『ハモりが完璧やな!』って思った(笑)」
■tricotがポストロック的な複雑なサウンド構造をしているのに対して、グッドモーニングアメリカは非常にシンプルなギターロックで。つまり、イッキュウさんが言ったように音像的には真逆なんですけど、どちらのバンドも歌とメロディが真ん中にあるっていうところは大きな共通項だと思うんです。そういう点で感じるシンパシーみたいなものはあったりしたんですか?
金廣「いや、まだそこまで感じることはないですね。1度だけ対バンしたくらいなので。音楽的なシンパシーとかを感じたりっていうのはまだないんですよね。だからそこは今回、楽しみで」
イッキュウ「私もそうですね。ここまで真逆の色のバンドとこうして直接一緒に回るのは初めてなので、そこから得られるものがめっちゃ楽しみですね」
■そもそも、それぞれのバンドの楽曲って、どういうふうにできていくんですか?
金廣「ウチは全部、僕が作りますね。ドラムだけ『お願いします』っていう感じで。アレンジまで大体は自分でやっちゃいますね。ある程度頭の中で作って、書き出して、また構築したものをメンバーに渡して、そこからまた自分に戻してっていう感じです。ギターソロも作るし(笑)」
イッキュウ「ウチと真逆ですね。私達はまったく何もないところから、みんなでスタジオで作るんです」
金廣「へー! いいなぁ、それ……。楽しそう」
イッキュウ「(笑)。それで、オケが全部できてから最後に歌を乗せるという感じで。歌乗せる側から言うと、拍子も変わるし、複雑で意地悪なオケなんですけど(笑)」
金廣「確かに意地悪だね(笑)」
イッキュウ「ほんとに、『これに歌を乗せるの!?』っていうこともあるんですよ(笑)。でも、それが楽しみだったりもするんですけどね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 矢島大地
『MUSICA 1月号 Vol.69』のご購入はこちら