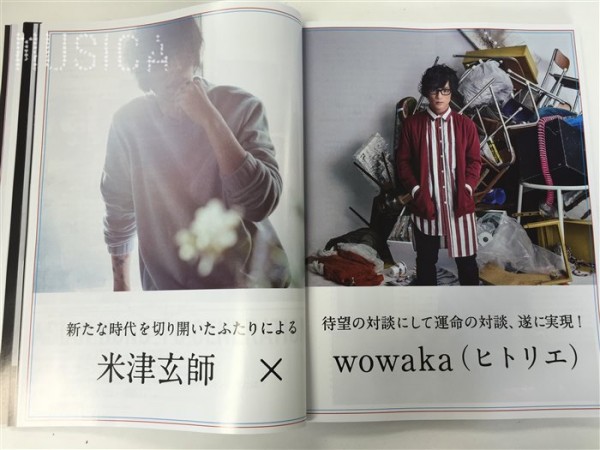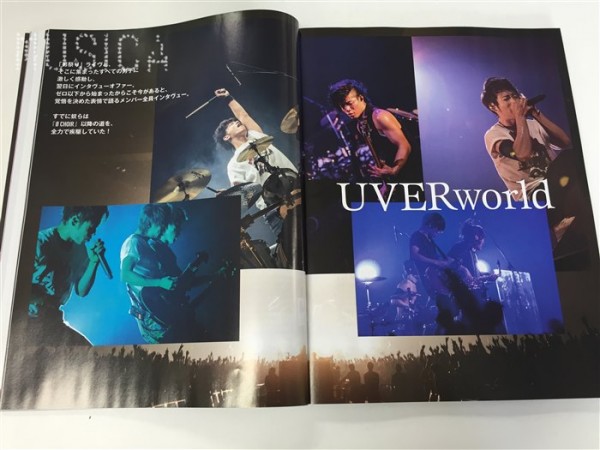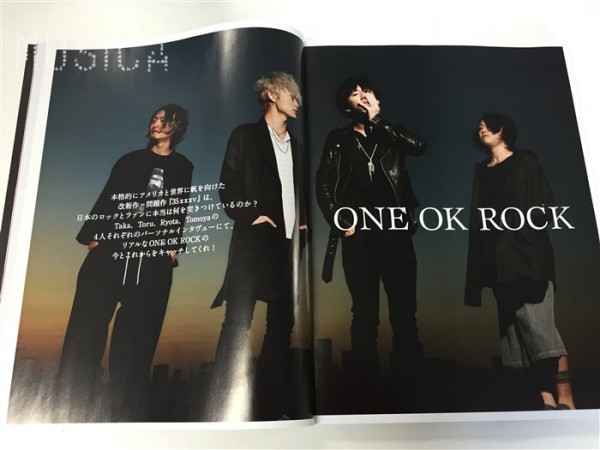KEYTALK、
『FLAVOR FLAVOR』で再び掴んだ自分達らしさ
――「全員がフロントマン」の自覚と武器

もっと4人の気持ちを固めて、共有して、
発信していかないといけないと思った。
やっぱりKEYTALKって、
誰かひとり強いフロントマンがいるバンドではないので。
全員がフロントマンのバンドだから、
意見を共有しなきゃ次のステージは目指せないと思ったんです
『MUSICA 3月号 Vol.95』P.114より掲載
■今回はタイトル曲の“FLAVOR FLAVOR”が首藤さんの作詞作曲、カップリングの“ナンバーブレイン”と“Stand By Me”がそれぞれ小野さんと寺中さんの作詞作曲っていう、3者3様のカラーが並んだシングルになっていて。特に“FLAVOR FLAVOR”は、前作の“MONSTER DANCE”のようなダンサブルな要素を引き継ぎつつ、ポップでメロディアスな要素も全面に出された曲だなと思うんですが。
首藤義勝(Vo&B)「まさに今おっしゃっていただいた通りなんですけど、踊れる要素とポップスとしてメロディが綺麗であるっていうところの両方を1曲にまとめたいっていうのが大本にあって。ノれる音楽にもいろいろあると思うんですけど、今までよりもテンポをちょっと落として、個人個人がパーソナルな空間で踊れるっていうのを目指して、アッパー過ぎず、グッと身体がノれるようなサウンドを作っていきましたね」
八木優樹(Dr)「いつもみたいに勢いとかエッジのある感じで攻め立てるんではなくて、大きいビートの中で16ビートを刻んでるような。だからグッとテンポを落とすことによってメロディは入ってくるんだけど、僕としては一つひとつの音への集中力が速い時よりも増してるっていうか、テンポが速いと気にならなかった部分もわかるので――」
■粗が気になって、いつもより難しかったんだ?
八木「かなり(笑)。如何に自分が勢い任せに叩いてたかっていうのがよくわかって。ハイハットのどの部分にどの角度で当てないと一定にならないとか、置きにいくとノリが全然出なかったり(笑)。いつもとは違うビートの捉え方で、今回はもっと細かいところも感じてやったつもりですね」
寺中友将(Vo&G)「でも、テンポ感の話もそうですけど、今までこういう雰囲気の曲をやってきてなかったわけではなくて。今までもこういう雰囲気の楽曲はあって、個人的にはそういう曲が凄く好きで。だから、KEYTALKの初めての一面じゃなくて、元々僕らにあった一面を前面に押し出していくっていう感じですかね」
■逆に言うと、こういうメロディアスな側面とか少し遅いテンポ感で横ノリっぽいグルーヴのような、これまでもあったのに隠れてた一面っていうのを今回はちゃんと全面に出してやりたかったっていう想いもある?
寺中「それは今までずっとあった感覚ですね。俺と同じようにこういう曲のほうが響きやすい人もたくさんいるんじゃないかと思ってて……これがKEYTALKの本当のよさだって思ってるわけじゃないし、別に『こういうことができるんだぞ』っていう感じともちょっと違うんですけど。でも、たとえば僕らのYouTubeに上がってるような曲しか知らない人達にとっては新しい一面なのかもしれないし、ここからバンド自体の音楽性を広げていく上でだったり、大きいステージでやっていく上で、絶対必要になってくる部分だなとは思うんで。そこへの第一歩のチャレンジですね」
小野武正(G)「やっぱりこの曲はしっかり歌を聴かせていきたいっていうところもあって。そこで今までのKEYTALKの流れを汲んでいろいろぶつけるっていう手法でもよかったと思うんですけど、そうではなく、結構ストレートな曲になるように意識したと思います。もっと広いフィールドでのお客さんが相手だっていうのは、みんなで話した中で出てきたキーワードだったりもしたんで」
■みんなで一度そういう話し合いをしたんだ。
小野「そうですね。昔はあんまりしなかったんですけど、ここ最近のKEYTALKは結構話し合いをすることが多くて。それがバンドとしての一番大きな変化ですね」
■なんで話し合いをするようになったの?
小野「やっぱりしっかり言葉にして共有していかないといけないなって思って。今までは割と流れに沿って、そんなに具体性を帯びた会話をせずにここまで来てしまった感があったので、今もう1回引き締めて、4人一致団結したいっていう想いがあったんですよね。そのほうが今後のスタンスとしてはいいのかなって気がして」
■それは、「俺ら、一度ちゃんと話し合おうぜ」っていうことを誰かが言い出したっていうこと?
小野「僕ですね、僕が言い出しっぺです。たぶん去年の10月くらい頃だった気がしますね、今までもミーティングとか話し合いはしていたんですけど、より密な会話をするようになったんですよね」
(続きは本誌をチェック!)
text by 寺田宏幸
『MUSICA3月号 Vol.95』