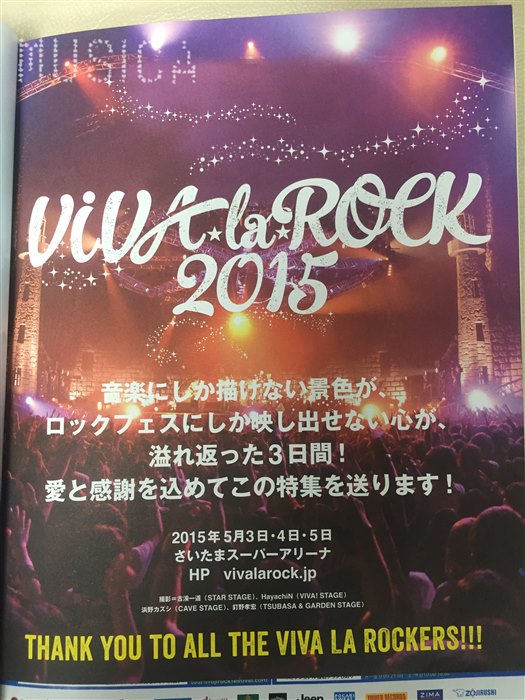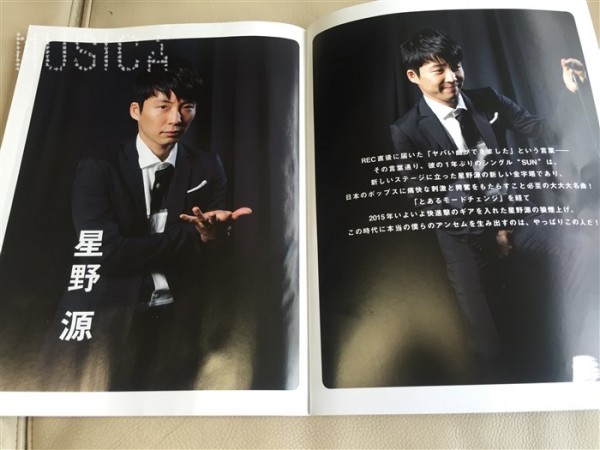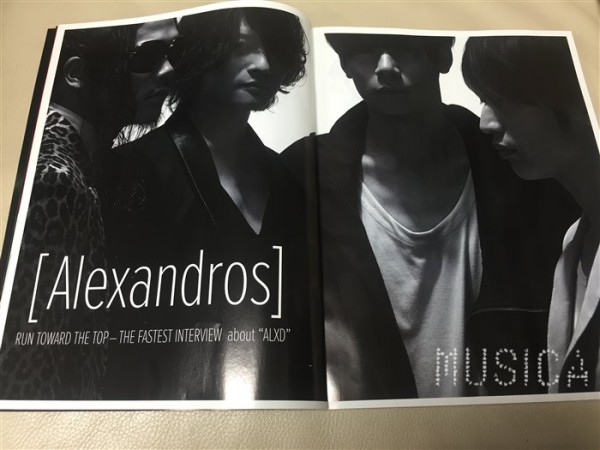MUSICA presents
降谷建志スペシャルトークセッション&爆音先行試聴会
at Red Bull Studio Hall

たくさんの方にご応募いただいた「MUSICA presents 降谷建志スペシャルトークセッション&爆音先行試聴会」、2015年5月23日(土)に青山にある「Red Bull Studio Hall」にて開催し、おかげさまで大盛況の中、とても楽しく貴重なひと時を過ごすことができました。
この企画は、Dragon AshのKjこと降谷建志がソロプロジェクトをスタートするにあたり、その第一声を表紙巻頭で伝えたMUSICA2015年4月号の購入者特典として応募を募り、抽選で100名様をご招待して開催したスペシャルイベント(MUSICA4月号はこちらから)。


降谷建志としては今回が初めてであるのはもちろん、Dragon Ashとしても普段こういった形で公開トークセッションや試聴会をすることがほとんどない中で、とても貴重な機会を一緒に作ることができました。
今回のイベントは、6月17日にリリースされるファーストアルバム『Everything Becomes The Music』収録楽曲から、MUSICA4月号でいち早くその詳細を語った5曲プラス1曲という全6曲の試聴と、降谷本人を迎えてのトークライヴという形で構成。みなさんに爆音試聴していただいた楽曲のうち、配信シングル“Swallow Dive”とシングル“Stairway”以外の4曲は未だ世の中に発表されていない、まさにこの場が初公開となる楽曲でした!
イベント開始と同時に、何はともあれまずは3曲を試聴。“Swallow Dive”に始まり、変則的に組み上げつつも疾走感のあるリズムに乗って伸びやかな歌が舞い踊る“P Board”、壮大なサウンドスケープの上で柔らかで美しい歌が響く“Wish List”と、MUSICAでも語ってもらった楽曲群を特設スピーカーから爆音再生。全国各地から集まってくれた参加者の皆さんは誰もが初めて耳にするその音に真剣な面持ちで聴き入っていて、高い集中力の中にもその興奮と喜びが伝わってきました。


その後、建志を呼び込んでトークセッションに突入すると、場内は一気に昂揚!(トークのお相手は編集長の有泉が務めさせていただきました)。「ひとりの人間という最小単位から生まれていく宇宙を提示したかった」等、ソロプロジェクトの意図に関する話題はもちろん、プライヴェートスタジオ「チェンバース」の写真やジャケット&アーティスト写真撮影時のオフショットなどのレアな写真をモニターに公開しつつ、すべての楽器の演奏やアートワークまで自ら手掛ける、その制作行程や秘話を交えつつ、音楽家・表現者としての降谷建志のこだわりや、彼の中に一貫して流れる思想をたっぷりと語ってもらいました。チェンバースの内部を写した写真をモニターに出した際は、建志から「え、これ何!? セクハラ!?」なんて言われたりもしましたが(笑)、たとえば「ドラムを録る時は、ここでRECボタンを押して、そのままドラムのところに走って行って、急いで叩き始めるんだよ!」といった具体的な話も語られ、本当に建志が日々ひとりきりで紡ぎ出した音が今回のソロの音楽になっているのだということが実感と共に伝わったと思います。笑顔も溢れつつ楽しそうに、かつ真摯に語ってくれる建志の姿に、最初はやや緊張気味だった雰囲気も次第にリラックスしたものになり、とても有意義な時間を過ごすことができました。

トークセッション終盤には会場内のお客さんから直接質問を募るコーナーも。「せっかくだから何でも答えるよ!」と言いながら参加者の問いに答えていった建志は、ソロプロジェクトのロゴに描いている黄金長方形の意味について熱く語ったり、Dragon Ashにおける作曲とソロでの作曲の違いを語ったり、あるいはラップやヒップホップはもうやらないのか?といった鋭い質問に答えたりと、建志自身も貴重なファンとのコミュニケーションを楽しんでいる様子が感じられました。
その後、本人もその場で一緒に再び3曲を試聴。こちらも初公開となる“One Voice”、“Angel Falls”、そして先行シングルとして5月20日にリリースされたばかりの“Stairway”の3曲という、最初に聴いた3曲とはまた違ったタイプの楽曲群を爆音で再生。建志も「こうやって一番近いファンに最初に聴いてもらうのはすげぇ誠実な形だと思うし、いい機会だね。恥ずかしいけど(笑)」と言いながら、自ら参加者に「ねぇ、英語詞と日本語詞だと、みんなはどっちのほうがいいの?」と問いかけるなど、そのダイレクトなリアクションを興味深く受け取りながら試聴を楽しんでいました。
最後はお客さんとの記念撮影も行い、イベントは終了。終了後、建志は「すげぇ楽しかった!」と満面の笑みで言ってくれましたが、参加してくれた皆さんはいかがでしたか? 最初に書いたように彼とファンがこういう形で交流する機会はほとんどないので、建志本人にとっても参加してくれた方々にとっても、ライヴとはまた違う形でお互いの「同志」を認識することができた貴重な機会となったのではないかと思います。そしてもちろん、我々MUSICAにとっても。本当に楽しく、有意義なひと時でした。
建志さん、集まってくれた皆さん、そしてご協力いただいたRed Bullの皆さん、レコード会社ならびにマネジメントのスタッフの皆さん、本当にありがとうございました!
なお、4月号のソロ第一声に続き、完成したアルバム『Everything Becomes The Music』についてのインタヴューを、次号6月15日発売のMUSICA7月号に掲載します! こちらも是非お楽しみに!!