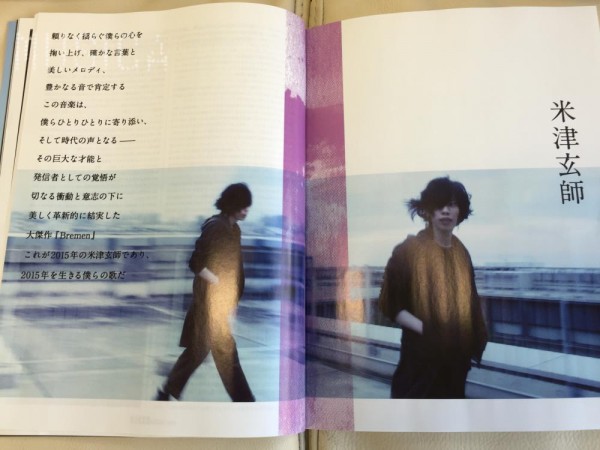KEYTALK、初の武道館を目前に控え、
改めてSG『スターリングスター』でこのバンドの鍵を深く掘る

僕達も以前はフラストレーションがあったんです。
踊れる4つ打ちがどうこう言われて
腑に落ちない時期も確かにあったんですけど、
最近そういう愚痴は言ってないなって思って。
本当に今が楽しいんだろうなって改めて思います(首藤)
『MUSICA 11月号 Vol.103』P.86より掲載
■10月28日の武道館、圧巻のソールドだそうで。
首藤義勝(Vo&B)「凄い嬉しいです! ずっと得体の知れない武道館って場所に対して、半分怖い思いがあったんですよね。でも、チケットがちゃんとはけてたり、日程が近づいてくるにつれて、だんだん現実味を帯びてきて。今は楽しみな想いのほうが強くなってきてますね」
八木優樹(Dr)「今までの最大キャパがZepp Tokyoなんで、武道館はおよそ4倍に迫るぐらいの大きさで……だから凄い怖かったんですけど、それだけの人達が僕らに期待してくれてるっていうのが凄い嬉しいなって思って。なので、最近は『やってやろう!』って気持ちになれてきましたね」
寺中友将(Vo&G)「そうだね。今までの東京でのワンマンの時も、たとえば『Zeppをやる前にこの会場が決まってる』みたいな時に、予約の時点ですでにZeppの枚数を超えてたんで――」
■常にキャパが足りない場所でやって来たし、そのスピード感で自分達も進化できてたってこと?
寺中「はい。で、Zeppの次は武道館っていうのは普通の流れだと思うんですけど、前回のZeppの時点で聞いた時の予約の人の数って1万人も来てなかったんですよ。だから最初は完全に不安しかなくて。なので、今はホッとしたっていうのが一番ですね(笑)。僕ら、ここ2~3年の雑誌のインタヴューとかで『武道館を目標にしてます』ってずっと言ってきてたんですよね。だから僕らはもちろん、きっと前からKEYTALKのこと知ってくれてた方にとっても凄く特別な場所だと思うんで、もう全国からたくさんの人が応募してくれたんだなって思いました。とりあえず初めての武道館っていうことで、みんながお祝いに来てくれるみたいな印象です」
小野武正(G)「僕は今最高の気持ちですね。『最高!』って気持ちと、『やってやるぞ』という闘争心……ですな!」
首藤・八木・寺中「『ですな!』って何なんだよ!!」
■(笑)「ですな」って言葉のオッサン臭さとは真逆のキラキラした表情で言ってますが、武道館って夢の場所だったんですか?
小野「夢のまた夢でしたね。『無理っしょ』って思ってましたけど、ちょっとずつ現実的になっていって、『絶対やってやるぞ!』っていう場所になりました。なので、満を持してやれる感じはします。『イェーイ!』って感じ……ですな(笑)」
■全部「ですな」で済まそうと思うな!
一同「ははははははははははははははは!」
小野「すいません(笑)。でも、本当によかったですね。恵まれてる環境のおかげだとも思いますし、僕らがこれまでやってきたことが報われたなっていう気持ちです」
■その武道館あっての今回のシングルの表題曲の“スターリングスター”だと思うんですが。この曲って、『ドラゴンボール』のタイアップっていうことと、武道館に辿り着いたっていうダブルミーニングなんですか?(とソングライターの首藤くんに問う)
首藤「結果的にそうなった感じですね。元々武道館をテーマにしてたし、シングルリリースも10月って前から決まってたんで、武道館に合わせるのがタイミング的にちょうどいいなって思ってたんですよね。このタイミングで自分達の今の状況を歌ってるリアリティのある曲が出せたら、武道館に向けて余計説得力が増すんじゃないかと思って作りました」
■<スター>っていう言葉も含め、歌詞には『ドラゴンボール』感も入ってますよね? 後でタイアップが決まってから歌詞を考えたってこと?
首藤「そうです。まだ歌詞が書き上がってない時にタイアップのお話をいただいたんですけど、その時点では闇に入ってる歌詞を書いてたんです。でもその歌詞を意識し過ぎたら作詞に詰まっちゃいそうだったんで、大元のテーマである武道館のことをだけ考えようと思って。でも、結果『ドラゴンボール』のほうにもはまりそうな感じになりました(笑)。曲調自体はここ1年ぐらいずっと考えて作ってたんですけど、ビートをちょっと大きめにして、体は動かせるけどメロディは犠牲にしない曲がいいなって思ってて。あと、大きい会場で映える曲が作りたいなって思ってたんです」
■それがこの雄大なグルーヴ感に繋がってくるんだ。曲を聴いてL’Arc~en~Cielの“snow drop”を彷彿としたんですけど。音からウィンターソング的な匂いを感じた部分も含めてね。
首藤「おぉ! “snow drop”大好きです。確かに、歌詞変えたらウィンターソングにもなりそうですよね。嬉しいです、ありがとうございます!」
八木「この曲を最初に聴いた時は、義勝らしいいい曲だなって思いました。最初はもうちょっとファンキーでアッパーな感じだったので、そういう勢いのあるロックに寄せたいのかなって思ってたんですよね。でも、プロデューサーのNARASAKIさん含め、みんなで話し合っていく中で、もうちょっと雄大な感じを出そうってなって、テンポをグッと落としたんです。それがいいふうにはまったのかなと思います」
寺中「歌詞に関しては――僕、自分以外の人が作った等身大の歌詞を歌うのって初めてだったんです。昨日ライヴで初めてやったんですけど、自分の曲を自分で歌うのと、義勝が作った曲で自分達のバンドのことを歌うっていうのが、似てるけど凄く大きな違いがあるだろうなって思ったんです。でも“スターリングスター”は今までになく自分の世界に入り込める曲だなって思ったし、それって初めての感覚で。もちろん世の中に向けて出す曲なんで、リスナーにどう届けるかが大事だと思うんですけど、今回のこの曲に関しては、自分に一番響いてる印象があるし、だからこそ新しい気持ちで歌えるんだなって思います」
(続きは本誌をチェック!)
text by鹿野 淳
『MUSICA11月号 Vol.103』